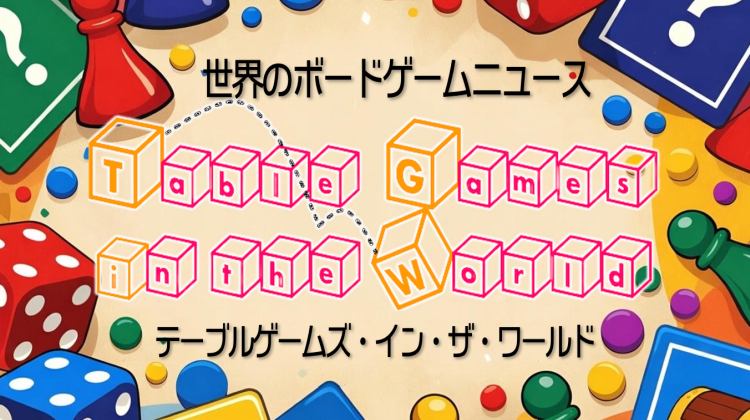フェイス・トゥ・フェイス(Face to Face)
誰かに見られてる
目と鼻と口のパーツを並べて手札をなくすことをめざす配置ゲーム。手番には裏になっているタイルを1枚引いて、手持ちから1枚を場に配置する。ルールは簡単で、目と口は接してはいけないことと、接するタイルは同じ色でなければならないこと。誰かが手札をなくしたとき、残りの人がもっているタイルが得点になる。
ゲームが始まってすぐ、お互い邪魔するとゲームが終わらないことに気付く。そこで貴重な鼻タイルを積極的に出したり(出さないとすぐ手詰まりならぬ鼻詰まりになる)、鼻タイルの回りにできるだけ多くのタイルが置けるよう隙間を作ってあげたり。そんな協力プレイで、何とか山札がなくなるまでは行ったものの、結局全員置けなくて終了ー。
タイルは大きさも形もバラバラで、しかも引いてみるまで目か鼻か口か分からないので、戦略の要素はほとんどない。あえて言うなら、わずかな隙間に置ける小さいタイルを積極的に取ることくらいか。
そんな勝ち負けよりも盤面に現れたピカソのような顔、顔、顔のインパクトを楽しむのがよさそう。私は途中で気持ち悪くなってしまったが。ふうかさんは目のタイルを両目に当てて遊んでいたが、ゲーム中、皆おかしくなっていたようだ。
Face to Face
A.ベアード/アンテイムドゲームズ(2009年)
2〜4人用/8歳以上/30分
・プレイスペース広島:フェイス・トゥ・フェイス
・ふうかのボードゲーム日記:フェイス・トゥ・フェイス
ザヴァンドールの鉱山(Die Minen von Zavandor)
宝石でレベルアップ
『ハンザ・テウトニカ』を遊んでいて思ったことだが、ドラクエ世代にとってレベルアップはとても楽しいものだ。この作品では、毎回異なるアイテムや種族を手に入れ、レベルアップしていく。これが楽しくないはずはなかった。
『アグリコラ』と『ルアーブル』がブレークしたルックアウトゲームズは、創業10周年としてこれまでにないほど多くのゲームをリリースし、更なる飛躍をしようとしている。その中の1作は、かつて発売された『ザヴァンドールの王笏』『ザヴァンドールのドラゴン』に続くザヴァンドールシリーズ。とはいえ前作とは作者もシステムも全く異なる。来月のエッセンで発売される新作なのに、もう日本語版が先行販売されているとは嬉しい。
プレイヤーはドワーフとなって、宝石を掘り、その宝石を入札してアイテムや種族を取り、レベルアップするというボードゲーム。流れはシンプルで、プレイヤー同士の交換は同時に行われ、カードのテキストは多くない。またラウンド数も少なめで、これまでプレイヤー人数×30〜45分だった同社のプレイ時間を短縮しようとしたものだろう。
まず山から宝石を取る。宝石の山は4つあり、それぞれ取れる宝石が異なる。最初はサファイアが多い山からしか取れないが、アイテムによってダイヤモンドやルビーなどより高価な山にアクセスできるようになる。ただサファイアの山にもたまにダイヤモンドなどが入っているのが面白い。
とはいえ、高価な宝石も集めていなければただの石。そこでプレイヤー間で自由かつ同時に交換できる。口先の達者な人が有利かと思ったが、実際やってみると、ほしい宝石とそうでない宝石がはっきりしているのと、銀行では確実に2対1交換できるので、思ったよりずっとスムーズだった。
交換が済んだら入札。4種類の宝石をまとめて伏せて出し、1種類ずつ、一番多く出した人がアイテムや勝利点を取る。アイテムは予め公開されており、どのアイテムを取りたいかによって、交換で集める宝石も変わるだろう。ほしいアイテムがかぶったり、前にとったアイテムとのコンボができそうになったりすると、交換から駆け引きが生まれる。
最後に手持ちのアイテムのレベルアップ。こちらにも宝石が必要で、入札で使いすぎないように注意したい。レベルアップすることにより、山から取れる宝石が増えたり、入札が有利になったり、ボーナスの勝利点が入ったりする。自分が最初から持っている種族のレベルアップもお忘れなく(最初の種族は、全員同じか、それぞれ一長一短あるかを選べる)。
これでラウンド終了。数ラウンド繰り返して、最後にゲーム中手に入れた勝利点と、完成=最高レベルに到達したアイテム・種族の勝利点で勝敗を決める。アイテムをたくさん取っても、完成していなければ勝利点にならないので注意したい。
今回は宝石を増やす種族のカードが前半でなかったために全体的にジリ貧。入札で大盤振る舞いすると後が続かない。サファイアの宝石コンボができた私は、毎回「サファイア下さい。エメラルドあげます」と言い続けていたが、警戒されてじきに交換してもらえなくなった。そのためレベルアップも滞り、後半の伸びを欠いて3位。karokuさんがアイテムフルコンプで1位。
アイテムの出る順序によって、各アイテムの重要度が変わり、展開も大きく変わると思われる。ドワーフというテーマにはピンと来なかったが、アイテムのレベルアップと入札の駆け引きが面白く、また遊びたいと思わせる要素たっぷりだった。
Die Minen von Zavandor
A.プフィスター/ルックアウトゲームズ(2010年)
2〜4人用/8歳以上/45〜90分
・ふうかのボードゲーム日記:ザヴァンドールの鉱山