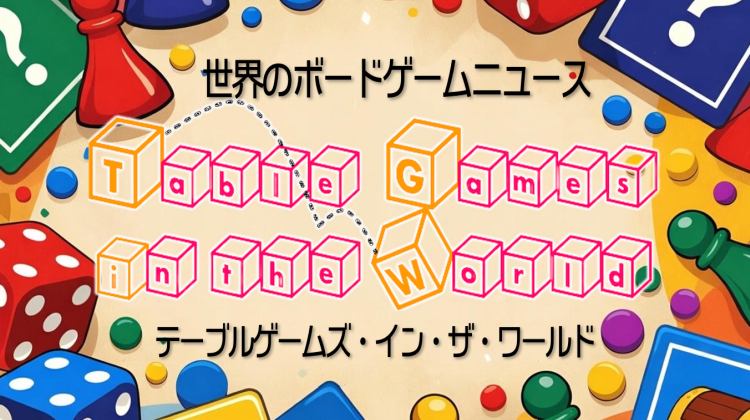ボードゲーム紹介:指輪物語:旅の仲間たちトリックテイキングゲーム(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Trick-Taking Game)
忍び寄る影にどう立ち向かう?

映画にもなったJ.R.R.トールキンのファンタジー小説『指輪物語』のストーリーに沿って進める協力トリックテイキングゲーム。国際ゲーマーズ賞ファイナリスト、ゴールデンギーク賞協力ゲーム部門、ミープルズチョイス賞6位。映画に出てこない部分も盛り込まれているので、小説を読んでいたほうがピンと来やすいが、協力トリックテイキングゲームのメカニクス自体が面白いので、知らなくても十分楽しめる。
今回の章の登場キャラクターと特別ルールを確認し、登場キャラクターをドラフトする。多くの章では「指輪の1」を持っているプレイヤーがフロド。各キャラクターには達成条件があり、全員が達成できればクリアとなる。
トリックテイキングは切り札なしのマストフォロー。指輪のスートも切り札ではないが、「指輪の1」だけ、必ず勝つことができる。ただし最初は指輪のスートではリードできず、フォローできなくて誰かが出した後でようやくリードできるようになる。
各プレイヤーが達成条件をもち、シナリオが進むごとに難しくなっていくのは『ザ・クルー』にも見られたが、キャラクターメインで、必ず全員に1枚ずつタスクが割り振られるところが異なる。達成難易度に差はあるものの、「他の人の邪魔をしなければ特に何もしなくてよい」という状況が起こりにくく、自分の目標達成のためにどこかで頑張らなくてはいけない。目標同士がぶつかることもあり、さらに章ごとに達成を阻む新ルールが追加されるため、どちらを優先していくかが悩ましい協力のポイントとなる。
さらに章が進むとさまざまな趣向が凝らされ、ゲームは全部で18章あるが、ロング(何ディールか行って登場キャラクターの目標を全部達成する)になる第9章ぐらいから格段に難しくなる。成功すれば次の章、失敗しても何度も挑戦したくなるので、気がつけば1時間も遊んでいる。今春、CMONジャパンから日本語版の発売が発表されたが、指輪物語の第2部「二つの塔」のトリックテイキングゲームも発売され、これは第3部までいきそうだ。
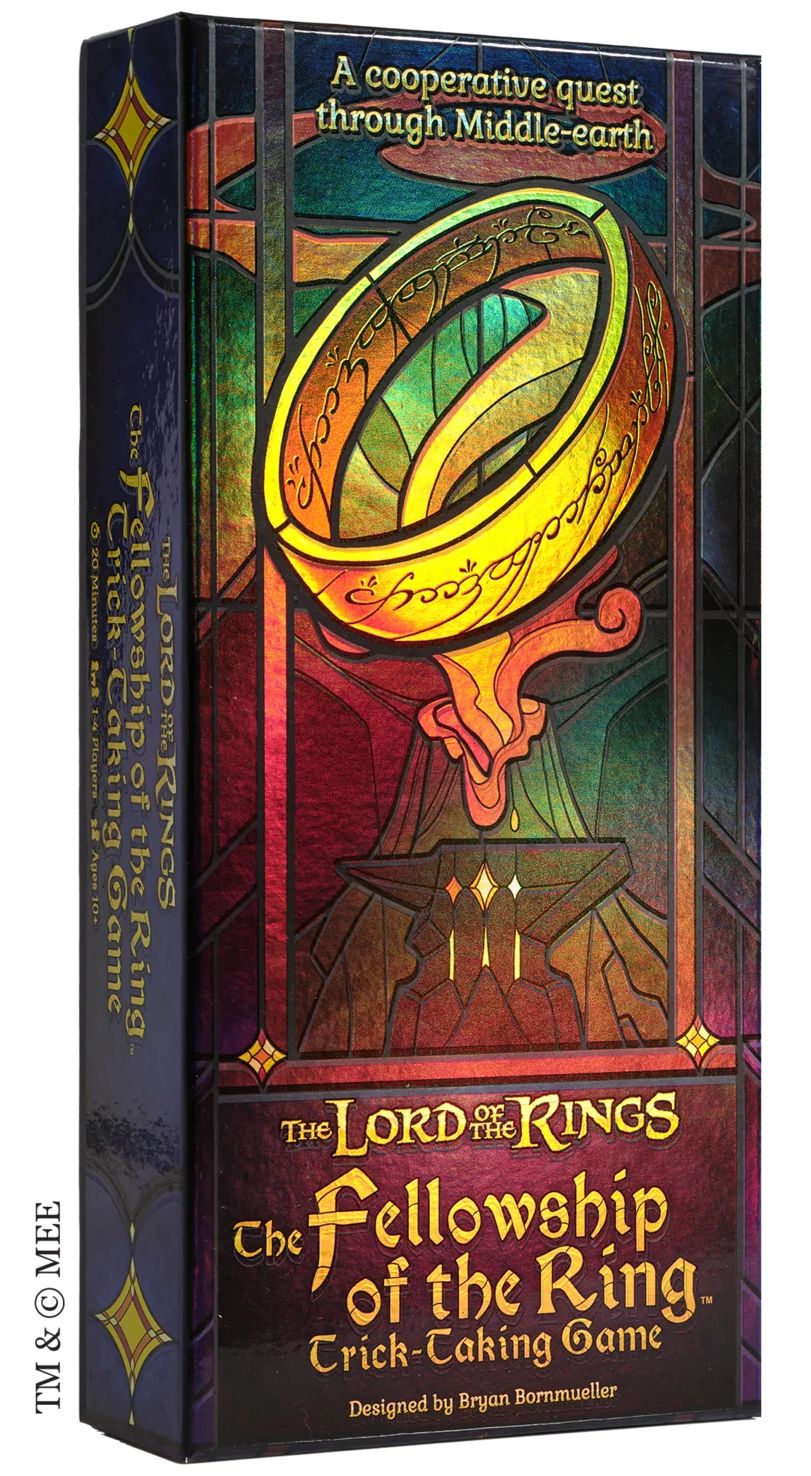 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Trick-Taking Game
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Trick-Taking Game
ゲームデザイン:B.ボーンミュラー、イラスト:E.ライアン&S.R.シモタ
オフィスドッグ(2025年)
1~4人用、10歳以上、20分
ジャック・ゼメ逝去、『ごきぶりポーカー』『おばけキャッチ』の作者

ボードゲームビートなどの海外ソースによると、『ごきぶりポーカー』や『おばけキャッチ』のデザイナー、ジャック・ゼメ(Jacques Zeimet)氏が2月5日に亡くなったことが明らかになった。
ゼメ氏は、ルクセンブルク人ということと、『オバケだぞ~』の作者M.シャネン氏と結婚していること以外、顔写真も含めプライバシーが一切明らかにされていないデザイナーである。エッセン・シュピールの会場ではドライマギアやドライハーゼンのブースに立っていたが、インタビューも写真撮影も拒否。ネット上にある写真も何ヶ月かかけて全部削除させたという。名前の読み方でさえ、フランス語風に「ゼメ」と呼ぶ人、ドイツ語風に「ツァイメット」と呼ぶ人、ほかにも「スィーメ」と呼ぶ人もいた。
しかしその作品群はよく知られている。『バンボレオ(1996)』がデビュー作で、30年の間に50作品以上を発表。日本語版になったものだけでも『ごきぶりポーカー(2004)』『グラフィティ(2007)』『おばけキャッチ(2010)』『おばけキャッチ2(2012)』『七人の探偵(2015)』『ドデリド(2016)』『ごきぶりデュエル(2017)』『ばったポーカー(2021)』『フラフー!(2021)』『おばけキャッチたんじょうびパーティー(2025)』がある。ドイツ年間ゲーム大賞は推薦リストに5回、アラカルトカードゲーム賞には10位以内に5回入賞。
いずれも極めてシンプルなルールで大人でも楽しめるものばかりでロングセラーも多い。新しい作品が遊べなくなるのは残念だが、傑作の数々はこれからも永く遊ばれ続けていくだろう。
Boardgame Beat: Jacques Zeimet Has Passed Away