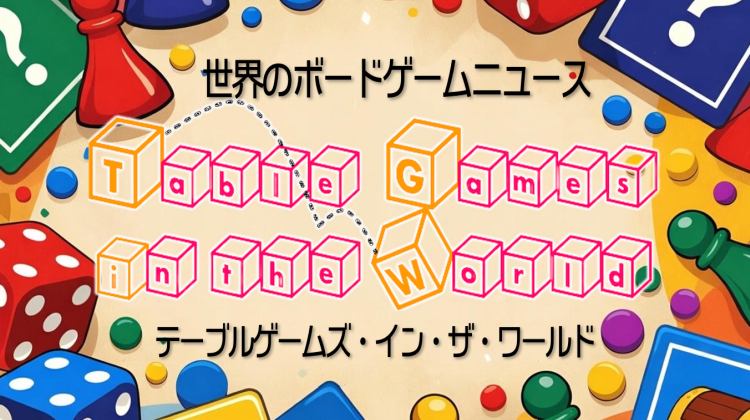アンケート:ドイツ年間ゲーム大賞2016予想
Q108:ドイツ年間ゲーム大賞2016、どれが大賞を取りそう?
| A.コードネーム 64票(40%) |
| B.インホテップ 33票(21%) |
| C.カルバ 62票(39%) |
今月18日にベルリンで発表されるドイツ年間ゲーム大賞。5月に3タイトルのノミネート作品が発表され、現在それらをみんなで遊んでみるフェイズになっています。どれが大賞に選ばれるか、あれこれ話をするのも楽しいでしょう。
アンケートは『コードネーム』と『カルバ』がどちらも4割程度で拮抗し、わずかに『コードネーム』のほうが多いという結果でした。審査員評で「多人数でもコミュニカティブな連帯経験を強調したい」というコメントから考えれば、『コードネーム』の可能性は十分にあります。『カルバ』と『インホテップ』は、まとめて「みんな同時にひとつのイベントに巻き込み、長い待ち時間が発生しない」と評価されています。
なお、昨年の予想は『街コロ』が1番(受賞したのは『コルト・エクスプレス』)でした。審査員の心中を読むのは容易ではありません。
7月のアンケートは定番ゲームを遊ぶ頻度です。怒涛のように押し寄せる新作ゲームを遊ぶのに精一杯で、棚の中にある名作・傑作の定番ゲームを遊ぶ機会が少なくなってはいませんか? 3択の中から近いものをご回答下さい。
大阪・中崎町にボードゲームカフェ、7月1日オープン
大阪・中崎町に7月1日、ボードゲームカフェ「賽翁(さいおう)」がオープンする。地下鉄谷町線・中崎町駅徒歩3分、9:00~22:00、不定休。
カウンター6席と、テーブルが4卓あり、最大で18人が入れる広さ。ボードゲームは国産・同人ゲームを中心に約200タイトルを揃える。少数生産のため入手難のゲームも多い。ルール説明は、店主が手が空いていればしてもらえる。
メニューは珈琲・紅茶・ジュースが500~600円、おともの軽食が200~300円で、一緒に頼んでも予算1000円以内で収まる程度。店主こだわりの珈琲・紅茶が用意されている。チャージ料はなく、2時間おきに1オーダーする。ゲーム中の写真などをプリントするサービス(1枚200円)も。
大阪はボードゲームカフェ・バーとプレイスペースの激戦地。営業時間や場所、ボードゲームのラインナップや飲食メニューなどによって、選択肢の幅がさらに広がることになる。
・ボードゲーム・カフェー 賽翁
ちょっと出かける用事のがあったんで、ボードゲームカフェの賽翁を見に行ってみた。
周りはお洒落な店がある中に、やはりお洒落な雰囲気。
こんな所でボードゲームするとかステキか(ノ´∀`*) pic.twitter.com/Vmu0Qajr15— レム単 (@k2h_7) 2016年6月28日