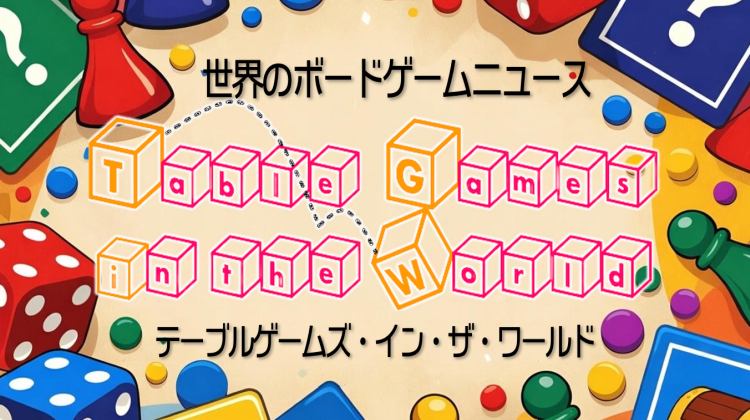春秋戦国の政治軍事競争『天下』日本語版、2月27日発売
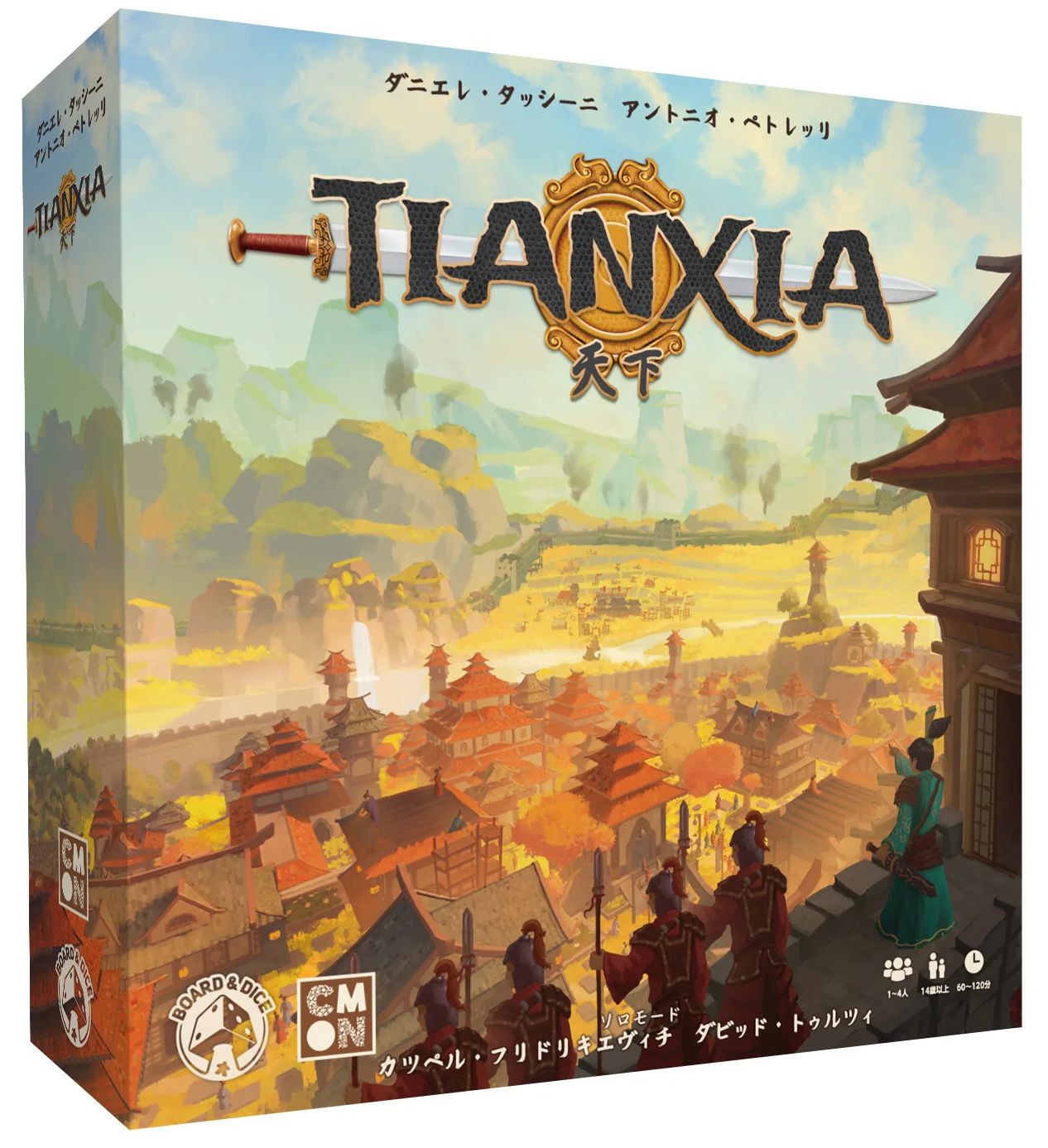 CMONジャパンは2月27日、『天下(Tianxia)』日本語版を発売する。ゲームデザイン:A.ペトレッリ&D.タッシーニ、イラスト:F.アブラヴァネル、1~4人用、14歳以上、60~120分、8800円(税込)。CMONジャパンショップ(下記リンク)の予約特典として、貿易ボーナスのプロモカードが付属する。
CMONジャパンは2月27日、『天下(Tianxia)』日本語版を発売する。ゲームデザイン:A.ペトレッリ&D.タッシーニ、イラスト:F.アブラヴァネル、1~4人用、14歳以上、60~120分、8800円(税込)。CMONジャパンショップ(下記リンク)の予約特典として、貿易ボーナスのプロモカードが付属する。
ボード&ダイス社(ポーランド)の新作でイタリア人デザイナーコンビがデザインした中国・春秋戦国時代が舞台のゲーマーズゲーム。プレイヤーは士大夫となり、戦国七雄と呼ばれる燕、趙、韓、魏、齊、楚、秦を支えて名声を競う。
4ラウンドで、各国に遊説家を派遣して君主の好意を勝ち取り、沿岸をゆく商船を通じて交易し、富や利権を獲得する。北辺では騎馬民族に備えて兵士を養成し、城壁や望楼を建てて侵攻を防ぐ。匈奴などの騎馬民族は、ラウンドごとに華北平原に向かって南進し、長城まで到達すると襲撃が発生して、全プレイヤーに影響を与える。
手番には地域、軍事、艀(はしけ)のいずれかのアクションを行う。地域アクションでは、7つの国のいずれかにアクションマーカーを配置し、その国の建物に為政家を置いて収入を得たり、港に停泊中の船と交易したりする。軍事アクションでは資源を支払って長城を建設したり、兵士を強化したりする。艀アクションでは川に船に労働者を乗せて収入を得るが、船には定員があり、先に来ていた労働者から追い出される。
アクションマーカーがなくなるか、アクションをしないことにしたプレイヤーからパスをして、全員がパスしたラウンド終了。パスが早いほうがボーナスの選択肢が多く、次ラウンドの手番順が早くなる。ラウンド終了時に4つの騎馬民族の襲撃チェック。襲撃があると戦闘になり、長城や兵士によって名声が入るが、戦闘に負けると騎馬民族は次々と南下し、建物にいる為政者を追い出すほか、南端までたどり着くと全員のお金と名声が減らされてしまう。
4ラウンドで集めた翡翠像、為政家の配置によって進めた宮殿トラック、目的カードの達成などの名声を合計し、最も多いプレイヤーの勝利。国選択、影響力の伸ばしどころ、防衛と交易の配分と、目先の利益だけでなく後のラウンドまで見据えて判断することが重要だ。シルクスクリーン印刷の木駒や組み立て式の船などコンポーネントにもこだわった作品。

アスドール・フランス年間ゲーム大賞2026ノミネート
 カンヌ国際ゲーム祭実行委員会は28日、アスドール・フランス年間ゲーム大賞(As d’Or – Jeu de l’Année)のノミネート12タイトルを発表した。一般、キッズ、中級、エキスパートの4部門について、この中から2月27日、カンヌ国際ゲーム祭会場にて大賞が発表される。
カンヌ国際ゲーム祭実行委員会は28日、アスドール・フランス年間ゲーム大賞(As d’Or – Jeu de l’Année)のノミネート12タイトルを発表した。一般、キッズ、中級、エキスパートの4部門について、この中から2月27日、カンヌ国際ゲーム祭会場にて大賞が発表される。
1988年に始まり、ジャーナリストやレビュアーからなる審査員によって選考されるゲーム賞。昨年は『オーディン』、一昨年は日本人作品の『トリオ』が大賞に選ばれている。キッズゲーム部門は2006年から、エキスパート部門は2009年から、中級ゲーム部門は2022年から始まり、昨年はそれぞれ『ヘーゼルナッツ作戦』、『クトナー・ホラ:銀の町』、『ビハインド』が選ばれている。
フランス年間ゲーム大賞は、ボードゲーム産業の多様性を周知するとともに、没入感をもって楽しむことができ、カジュアルプレイヤーにもコアプレイヤーにもリプレイ欲を喚起する作品を表彰することを目指す。基準は人を惹きつける中毒性、製品自体の独創性と美学(視覚的・戦術的な魅力)、ルールの質の3つで、著名なボードゲーム愛好家9名が選んでいる。
【アスドール2026ノミネート】
年間大賞部門(Jeu de l’année)
・フリップ7(Flip 7)
・リバース(Rebirth)
・トイバトル(Toy Battle)
キッズゲーム部門(Enfant)
・アルケオ(Archeo)
・ムーキの島(L’île des Mookies)
・まわるおばけの夜(La Valse des Fantômes)
中級ゲーム部門(Initié)
・ファーストラット(First Rat)
・テイクタイム(Take Time)
・ゼニス(Zenith)
エキスパートゲーム部門(Expert)
・アークス(Arcs: Guerre et déclin dans les confins)
・シヴォリューション(Civolution)
・アント(Fourmis)