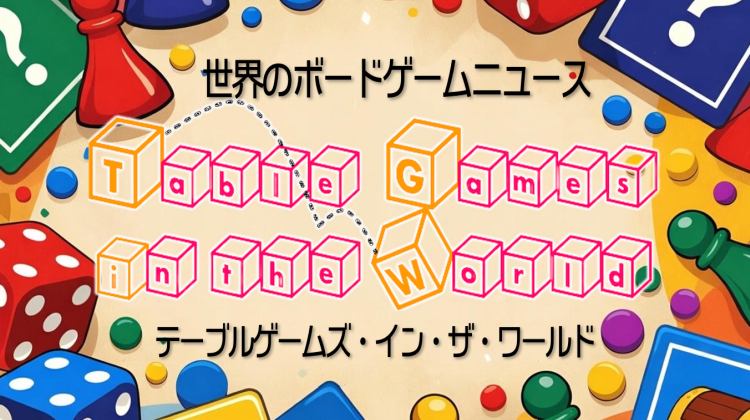国際ゲーマーズ賞に『エイジ・オブ・インダストリー』
 国際ゲーマーズ賞(International Gamers Awards)選考委員会は9月21日、先月ノミネートしていた作品の中から大賞を選出した。先週発表されたドイツゲーム賞よりもさらにフリーク好みの賞が選んだ今年のベストゲームは『エイジ・オブ・インダストリー』だった。
国際ゲーマーズ賞(International Gamers Awards)選考委員会は9月21日、先月ノミネートしていた作品の中から大賞を選出した。先週発表されたドイツゲーム賞よりもさらにフリーク好みの賞が選んだ今年のベストゲームは『エイジ・オブ・インダストリー』だった。
『エイジ・オブ・インダストリー』はイギリスのデザイナー、M.ワレスが『ブラス』をリメイクした作品。産業革命の初期、職人から機械へと急速に移り変わる中、資源を手に入れ、加工し、ネットワークを使って運ぶ。
ワレスの作品が同賞に選ばれるのは2004年の『蒸気の時代』に続き2回目。また今年のノミネート作14タイトルには、『エイジ・オブ・インダストリー』のほかに『ウェンズリーデイルへの最終列車』と『帝国の夜明け』が入り、ワレス人気を物語っている。
ワレスの作品は通常ツリーフロッグ社で限定販売されているが、近年は他社からメジャーデビューするケースも少なくない。『エイジ・オブ・インダストリー』はアメリカのメイフェア社が扱っている。国内では、テンデイズゲームズとプレイスペース広島が輸入している。
もうひとつの2人用ゲーム部門は、オバマ対マケインの選挙戦をテーマにした『キャンペーン・マネージャー2008(Campaign Manager 2008、リンク先はゲームストアバネスト)』が選ばれている。
・International Gamers Awards:2010 Winners
TGF2010、出展受付始まる
ゲームマーケットと並ぶ国内最大級のボードゲームイベント、テーブルゲームフェスティバルが今年も浅草で開かれる(11月28日(日))。その出展受付が昨日より、公式サイトで始まった。
出展区分は一般ブース・販売のみ(2,625円)、一般ブース・販売と体験(3,675円)、大型ブース(26,250円、2ブースで52,500円)の3種類。一般ブースで販売できるのは自費出版・インディーズのみで、大型ブースは体験卓が用意される。申込〆切は10月18日だが、予定数を上回った場合は先着順となる。
申込方法の詳細や申込フォームは下記の出展要項にて。
テーブルゲームフェスティバルでは、試作品のテストプレイを行うサークルが多い。ここでのフィードバックをもとに作品を練り直し、来年のゲームマーケットで製品販売するという流れだ。ゲーム制作中の方は、先日お伝えした萬印堂の試作品製作応援キャンペーンとともにこの機会を利用してみよう。
・TGF2010 F 出展要項