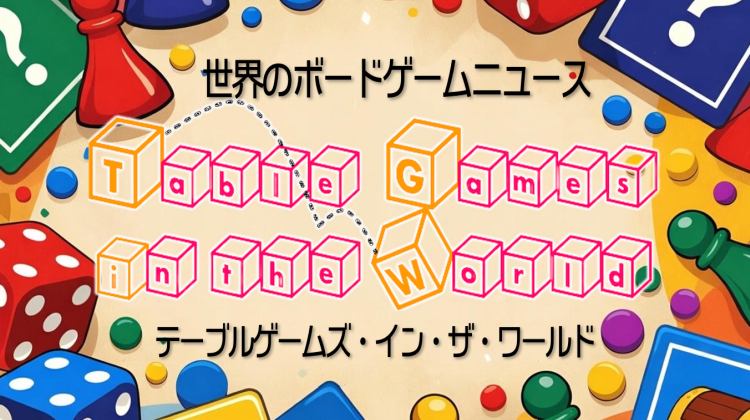中村誠デザインのミニチュアゲーム『武将列伝』、12月発売
 千葉・柏のホビースペース「ミスター・フィールド」は12月、ミニチュアを使ったボードゲーム『武将列伝 ベーシック』を発売する。デザイン・中村誠、イラスト・Mad、2人用、8歳以上、30分、4,980円(税別)。11月22日のゲームマーケット2015秋で先行発売される。
千葉・柏のホビースペース「ミスター・フィールド」は12月、ミニチュアを使ったボードゲーム『武将列伝 ベーシック』を発売する。デザイン・中村誠、イラスト・Mad、2人用、8歳以上、30分、4,980円(税別)。11月22日のゲームマーケット2015秋で先行発売される。
侍ミニチュアのシリーズ使って遊ぶ対戦型ゲーム。プレイヤー2人がそれぞれ真田幸村と伊達政宗を受け持ち、その部下である雑兵10体(騎兵、槍兵、弓兵、鉄砲兵、忍び)で部隊を編成し、対戦相手の武将を討ち取って勝利を目指す。
中村誠氏のデザインによって、ダイスを振るたびに変化する防御力、ヒモをつかった距離と範囲のシステム、豊富な特殊効果、スピーディな展開など、ミニチュアゲーム愛好者だけでなく、ボードゲーム愛好者でも楽しめるように作られている。
今後、織田信長、上杉謙信、武田信玄などの武将を加え、1人で2隊以上の部隊を率いたり、プレイヤー3人以上の大規模戦を行ったりできるようにしていくほか、1人用シナリオなども提供されるという。
内容物
武将ミニチュア 2体 雑兵ディスク 20枚 シナリオディスク 2枚
距離ヒモ 2本 陣ヒモ 2本 武将シート 2枚 刀剣カード 2枚
8面ダイス 2個 6面ダイス 28個 ルールブック 1冊

マクドナルド・ハッピーセットにボードゲーム、ドイツ
ドイツのマクドナルドは10月30日から、1ヶ月にわたってハッピーセット(Happy Meal)にボードゲームを付ける。提供はラベンスバーガー社で、R.クニツィアの『誰だったでしょう?』コンパクト版などが用意されている。
ハンバーガー、フライドポテト、ドリンクにおもちゃが付いてくるハッピーセット。日本では現在、プラレールとマイメロディ×リトルツインスターズが付録のおもちゃとなっている。
ドイツ・オーストリアのマクドナルドで今、付いてくるのはラベンスバーガー社のボードゲーム。『誰だったでしょう』『呪いのファラオ』『エルファーラウス』『ペンギンすべり』が並ぶ。いずれも5~6歳から遊べるコンパクト版だ。
同様のサービスは昨年にも行われており、その際には『メイクンブレイク』『ビリー・ビーバー』などが提供された。
・McDonald:Aktuelle Spielzeuge im Happy Meal