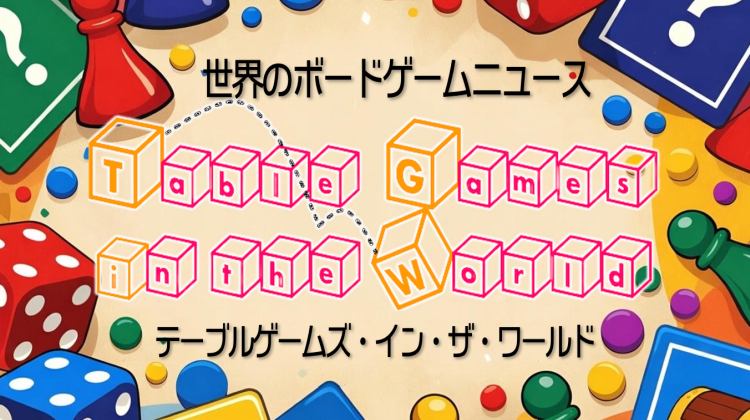シュピール’11:2日目
今日も何事もなく気になったゲームをプレイ三昧。人気のゲームは90分クラスなので卓がなかなか空かず、しばらく待った末に諦める。行ってすぐ卓が空くこともあるので、タイミングの問題だが、あいにく時間は限られている。開場の10時から17時はあっという間に過ぎた。
ピクトマニア(Pictomania)
「妻」「ガールフレンド」「花嫁」「婚約者」などの紛らわしいお題から1つを描き分けるお絵描きゲーム。チェコゲームズのフヴァキルの作品で、ペガサスシュピーレからも発売された。場には6枚のお題カードが並び、各自ランダムにお題が指定される。一斉に描き始めて、描き終わった人からほかの人の絵を当てに行く。早く当てるほど得点なので、絵は早く描き終わりたいが、早すぎると当ててもらえないジレンマ。難易度が変えられるのがいい。最難のレベル4は散々だったが、レベル1で貯めた分で勝利できた。早速ホビージャパンが発売を決定した模様(Czech Games Edition, 2011)。

モンキーランド(Monkeyland)
めくられたチップと同じサルを探すクニツィアの記憶ゲーム。サルはめくるたびに移動するので、場所が覚えていられない。大人用に難易度の高いバリアントもある。単純ながら2つ覚えるのでも精一杯だった。神尾さんが驚異の記憶力を発揮して1位。宿に帰ったらけがわさんが当然のように購入していた。(Sirius Products, 2011)
ダンジョンファイター(Dungeon Fighter)
ダイスを的の上に転がしてモンスターを倒す協力ゲーム。フェアプレイの人気投票でいきなり上位に飛び込んできた。ダンジョンを進むたびにモンスターが登場し、ダイスを的に向かって投げる。的には数字が書いてあり、その分のダメージを与えられるが、的から外れるとダメージを食らう。英雄によってさまざまな特殊能力があり、モンスターによって投げ方が指定されることもある。さらにショップで武器や道具を買えば、新しい攻撃ができる。そういう細かい設定が、ゲーム中の笑いを盛り上げる。三層目まで行ったが、机の下からダイスを投げさせるモンスターになかなかダメージを与えられず全滅。(Cranio Creations, 2011)

空いている時間は、小さいメーカーを回って気になったゲームの説明をしてもらい、気に入ったものを少々購入。このところ日本の代理店がマイナーなメーカーまで手を伸ばしてくれるので、たいていのものは日本で訳付きで手に入る。そのため、さらにマイナーなメーカーに挑戦できるようになった。
今日は早めに切り上げて、一路デュッセルドルフへ。快速で30分くらいかかるが、エッセンよりレストランの選択肢は広い。うろ覚えだったが何とか自家製ビールとムール貝料理が名物のレストラン「シュマッハ」に到着。10人ほどで楽しいひとときを過ごした。
盛り上がりすぎて帰りはぎりぎりになった。帰りの電車でけがわさんが読んでいたボードゲーム雑誌と同じ雑誌を読んでいる人がいて意気投合。聞けばエッセンの後、隣町のドゥイスブルクに行きウィスキーの試飲をしてきたという。相当へべれけで、買ったものを見せようとリュックサックを開けたら、『世界の七不思議:リーダー』がウィスキーの瓶と一緒に出てきたのには笑った。こんな飲兵衛さんでも、普通にボードゲームを遊んでいるのがすごい。
【フェアプレイ・スカウトアクション:木曜日18時】
1位:トゥルネー(パールゲームズ)
2位:ザ・シティ(アミーゴ)
3位:祈り、働け(ルックアウト)
4位:ローマに栄光あれ(ルックアウト)
5位:ヘルベチア(コスモス)
6位:キング・オブ・トーキョー(ハイデルベルガー)
7位:イノベーション(イエロ)
シュピール’11:1日目
今回のエッセン国際ゲーム祭は通訳や取材の仕事がなく、のんびりと過ごすことができている。そうなれば当然、実際にボードゲームを遊びにいく。各メーカーには試遊卓が用意されており、英語ではあるがインストもしてもらえる。実際にコマを動かしながら説明してくれるので、言葉を聞き落としてもだいたいは理解できる。分からなかったところは質問して、あとは1ラウンドくらい見ていてもらえば、正しいルールで遊べるし、原文のルールを読む手間も省ける。
シンガポール(Singapore)
建物を作ってさまざまなアイテムを手に入れ、お金や得点に換える拡大発展型のゲーム。後になるほど強い建物が出てくるので、適宜新しい建物に移動していかなければならない。黄色いキューブ「阿片」を手に入れたり、売って大儲けしたりできる建物は、建設時にブラックマーカーを引かなれければならず、これが溜まると罰金の危険が増す。その前にうまくさばいたり、贖罪したりしておかなければならない。阿片で大稼ぎし、後半は足を洗ったが、karokuさんが1点差の大逆転で勝利。(White Goblin Games, 2011)

アルバ・ロンガ(Alba Longa)
ローマ帝国の国作りゲーム。ダイスを振って1個ずつ取り、ダイスの色に沿って軍隊・現金・畑・信仰・モニュメントに人員を振り分ける。軍隊はほかのプレイヤーを攻撃し、現金はダイスを取るのに使い、畑は食料供給を増やし、信仰は収穫高を上げる。人口とモニュメントを増やすのが目標。序盤に軍隊がなかったばかりに袋叩きにあった神尾さんと私とふうかさんが沈み、その間に着々と人口を増やしたdjさんの勝ち(QWG, 2011)

シディ・ババ(Sidi Baba)
1人が盗賊の親方(マスター)となり、ほかが探検家となって迷宮を探検するゲーム。マスターはついたての裏地図を見ながら、探検家が今見える風景のタイルを出す。砂時計が落ちてランプがなくなる前に、宝箱を開けて洞窟を脱出しなければならない。協力ゲームだが、無事脱出できれば獲得コイン数で勝敗を競う。はじめは闇雲に走りまわっていたが、次第に入り組んだところも気がつくようになる。マスターの神尾さんが置いた岩がかえってヒントになって宝箱発見。そして脱出成功。今まで通ったルートを覚える空間認識力・記憶力が問われた。(Hurrican, 2011)

ドローデルおばさんのドレーデル(Tante Drodels Drödel)
実は本日遊んだ唯一のドイツゲーム。荷物を積んで、お題のコマとできるたけ同じ重さの木のコマを目分量で荷物を積む。最後に集めたコマを天秤にかけて、お題のコマと同じ重さ(天秤が一番水平)な人が勝つ。木のコマは25個も入っており、どれがお題になるか分からない。神尾さんが驚異の目分量で1位。(Zoch, 2011)

日本語版がホビージャパンから発売予定されている『祈り、働け』のドイツ語版が無事届いていた。印刷がぎりぎりで、本日は200部、あとは土曜日に届くという。作者ローゼンベルクが第二子の出産で忙しく、プロモカードは1枚だけに留まった。