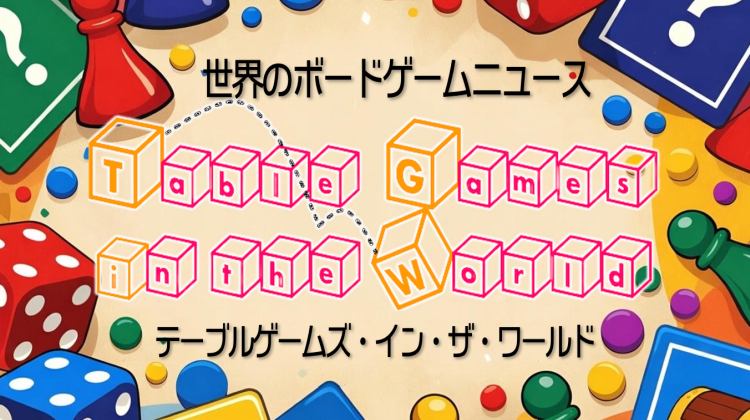ドイツ年間ゲーム大賞2009ノミネート発表
 ドイツ年間ゲーム大賞審査委員会は本日、今年のノミネートリストと推薦リスト、および特別賞を発表した。今年も5タイトルがノミネートされ、この中から6月29日、大賞が発表される。
ドイツ年間ゲーム大賞審査委員会は本日、今年のノミネートリストと推薦リスト、および特別賞を発表した。今年も5タイトルがノミネートされ、この中から6月29日、大賞が発表される。
今年のノミネート作品は、人気大爆発中の『ドミニオン』と『パンデミック』を漏らさず、かつプレイ時間40〜60分のミドルクラスを並べる顔ぶれ。ゲームになじみのない人に訴えながら、同時にフリークも満足させるリストとなった。
審査委員の発表では、協力ゲーム、カードゲーム、クイズゲーム、配置ゲーム、古典テーマのゲームと多彩なゲームを用意したが、いずれにも共通するのは「感情を呼び覚ましゲーム欲を誘う力」であるとしている。
同時に年間キッズゲーム大賞のノミネート、推薦リストも発表されている。
【ドイツ年間ゲーム大賞2009】
ノミネート:フィット(Fits / R.クニツィア / ラベンスバーガー)
〃 :ドミニオン(Dominion / D.ヴァッカリーノ / ハンス・イム・グリュック)
〃 :フィンカ(Finca / R.リンデ、W.ゼントカー / ハンス・イム・グリュック)
〃 :ファウナ(Fauna / F.フリーゼ / フッフ・フレンズ)
〃 :パンデミック(Pandemie / M.リーコック / ペガサスシュピーレ)
推薦リスト:モー、ポイズン、シティーズ、マオリ、ザックンパック、片目の海賊、ヴァルドラ、ダイヤモンドクラブ
特別賞(パーティーゲーム賞):ギフトトラップ(GifTrap / N.ケレット / ハイデルベルガー)
特別賞(新しいゲームワールド賞):スペースアラート(Space Alert / V.フヴァキル / チェコゲームズ)
【ドイツ年間キッズゲーム大賞2009】
ノミネート:オオカミと七匹の子ヤギ(Nicht zu fassen / F.モイヤーセン / ツォッホ)
〃 :ごちそう畑(Curli Kuller / M.トイブナー / セレクタ)
〃 :ツォーワボー(Zoowaboo / C.A.ロッシ / セレクタ)
〃 :魔法のラビリンス(Das magische Labyrinth / D.バウマン / ドライマギア)
〃 :島が見えた!(Land in Sicht! / S.ドーラ / ラベンスバーガー)
推薦リスト:ニムトジュニア、クリッカド、動物を見つけよう、ゴー!ゴリラ、シルエット探偵、黒い猫、小さな騎士トレンク、ダイスウルフ、警察アラーム
・Spiel des Jahres:Ausgezeichnete Spiele 2009
ゆうもあ賞2008に『ブロックス3D』
NPO法人ゆうもあは、ホームページにて2008年のゆうもあ賞を発表した。今回初めてとなる同賞に選ばれたのは『ブロックス3D』(ビバリー)。ほかに『カメのオリンピック』、『ネズミのメリーゴーランド』、『チーキーモンキー』がノミネートされている。
ゆうもあ賞は、新作ゲームの中から最もボードゲームの普及に貢献したと考えられるボードゲームを、ゆうもあ内の選考委員会で選ぶもの。ゲームの面白さだけでなく、ルールのシンプルでわかりやすいこと、同会が実施するイベントで遊ばれていること、国内流通が十分であることなどの条件が設けられている。
2月に発表され、『魔法にかかったみたい』が選ばれた日本ボードゲーム大賞は、会員・非会員を問わないボードゲーム愛好者一般の投票によって選出されるもので、ドイツゲーム賞のような位置づけになっている。今回制定されたゆうもあ賞はこれに対し、常日頃から子供や家族と接している専門のスタッフが選ぶ点でドイツ年間ゲーム大賞の位置づけに近い。
ノミネート作品ともども、お子さんのいる家庭ならぜひ試してみるとよいだろう。
・NPO法人世界のボードゲームを広める会ゆうもあ:日本ボードゲーム大賞2008ゆうもあ賞決定
・同:日本ボードゲーム大賞ゆうもあ賞とは
・ビバリー:ブロックス3D