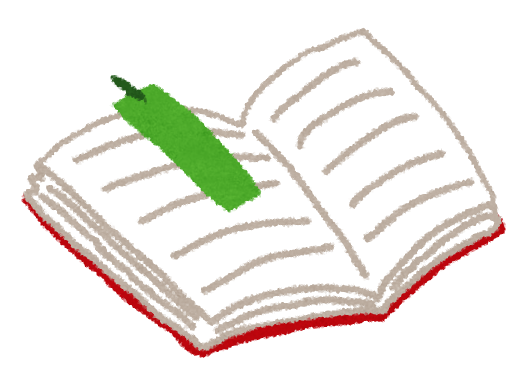年末にあたり梵網経の四十八軽戒を読んだ。十重禁戒は授戒のときにいつも読むが、その後の四十八軽戒はあまり知られていないのではないだろうか。その中で二十四番目に「大乗以外の教えを学ばない」という戒律がある(「もし仏子である汝が仏の経や律の大乗の教えや真正の見解・真正の本来の姿・真正の法身を知る機会をもちながら、それらを勤学して繰り返し馴染むことができず、七宝のような尊い教えを捨てて、逆に邪悪な見解―すなわち二乗や異教徒や世俗の経典・アビダルマ・様々な主題の諸論や書物や記録―を学ぶなら、仏性を断絶し、悟りの修行をさまたげるいわれとなるのであって、菩薩道の実践者ではない」)。筆者はほぼ毎年守れていないが、現代において大乗仏教の尊さは、他の教義と比較検討して初めて気づくものである。それどころか大乗仏教の特長を理解するにも、他の教義との対照があってこそだと思う。
本書は「価値」「知識」「推論」「言葉」「世界」「自我」「究極的存在」という七つのテーマについて、時代を超えた各宗派の見解をつきあわせ、さらに現代的な視点で批判的に論じるという「中間対話的アプローチ」を取った哲学書である。「入門」とはいえ、哲学についてある程度の素養がある人をターゲットにしているので、仏教についても思想面での関心や問題意識がないと難解かもしれない。それどころか研究者にとっても有益であり、本書が翻訳されたことは、細分化が進んだまま先細りしつつある国内の学界の発展につながりそうだ。
メインはインド哲学において正統派(ヴェーダの権威を認める)とされるバラモン教諸派であるが、仏教哲学も七つの章すべてに登場する。しかも説一切有部から、空を説く中観派、唯識を説く瑜伽行派に分けられ、それぞれの主張が注意深く検討されている。以下、仏教に関して、なるほどと思わされた箇所を何点か紹介したい。
第一章「価値」では善行と解脱の関係について。大乗仏教の実践は「自未得度先度他」の心によって行われるが、菩提心を起こしながら自身の菩提は後回しにするというのはどういうわけであろうか。寂天は『入菩提行論』において公平主義的な利他を説く。
苦しみを所有するする主体が存在しないなら、その苦しみはいったいだれに属することになるのだろうか。苦しみにはすべて所有者がいない。苦しみには違いがないから、それらの苦しみは、苦しみであるからという理由だけで、避けられるべきである。(61頁)
「究極的には人々は実在として存在せず、それら人々の間に何ら違いはない」というならば、「苦痛も、苦痛を和らげるための道徳的義務も究極的にはなくなってしまう」という著者は指摘するが、苦しみに自他の区別はないと考えれば、優先も後回しもなく、手当たり次第にできるところから救うということになり、菩提心と自未得度先度他は何ら矛盾するものではなくなる。前号で紹介した『理想的な利他』でいうところの「自利即利他」をこのように(本書の用語でいえば「還元論」で)理解することもできよう。
第二章「知識」では、諸法の実相が無常なもの=刹那に滅するものであり、「裸の個体」として捉えざるを得ず、名称などの認識は後付けの妄分別に過ぎないという法称の説が検討される。これが第四章「言葉」で唯名論(あらゆる言葉は虚構である)に、第七章「究極的存在」でブッダの全知者性(妄分別を離れて直接的に認識できること)につながる。この無分別智は、そっくりそのままではないが禅宗の「見性」や「悟道」の前身となるものであろう。
第三章「推論」では、「如来が死後に存在するかしないか」という問題についてブッダが無記を唱え、龍樹が「すべてのものは空であるかそうでないか」というかたちに一般化した四句分法の解釈について考察する。ブッダにおいては「そのような形而上学的空論は苦しみからの解放の達成に導くものではない」という考えが背景にあったが、中観派は「段階的教説」に基づき、矛盾があっても異なる聞き手にとってそれぞれ適切であればよく、すべては一つの同じ目的に導くものとして調和されるという。このように形而上学的な議論に踏み込まずに実践を重んじる考えは、第六章「自我」において、中観派(帰謬論証派)の「無我は最小限主義(存在に関する形而上学を前提としない)」という理解につながっている。著者は次のように述べる。
我々が自己同一性について判断をしたり、そうした判断への実際の関心を形成する際、人格に関して我々がもっているであろう何らかの形而上学的見解が必須というわけではない。還元論者と非還元論者のいずれにも反して、我々の同一性に関する「深い事実」があるかないかということは、我々の日常の規範的活動を正当化することはほとんど関係ないという。なぜならば、我々の日常的な活動は人格に関する形而上学に基礎づけられたものではなく、我々のおかれた環境や必要性に基礎づけられたものであるからだ。(278頁)
初期仏教は「非我」(自己というものはあるがバラモン教がいうような自己ではない)だったのが、次第に「無我」(自己自体が存在しない)と説かれるに及び、主体性や責任の問題が問われるようになるが、「自己が実際に存在するかしないかはさておきとにかく修行に打ち込む」ということは、道元禅師の「身心脱落」や「他は是れ吾にあらず」につながっていきそうだ。
仏教があくまで実践にこだわる傾向は、第七章「究極的存在」でも、ブッダの全知者性は覚りに必要な範囲に限られるという見解に表れている。法称の次のような引用から、インドで霊鷲山を参拝した日の夜、地元のインド人から「ブッダは人間の姿をした神様だからねえ」と言われ、「いいえ、ブッダは人間です。だからこそ人の苦しみを知り、それを乗り越える方法を示すことができたのです」という会話をしたのを思い出した。
この世全体の無数の小さな虫に至るまでの広範な知をもっていることにいったい何の意味があるだろうか。それよりもむしろ、我々が実践すべきことについての彼の知を求めよ。我々にとって、最も望ましい権威とは一切を[無差別に]知るものではなく、我々が望むのは、この世における繁栄をもたらし、何が捨てられるべきであり何が養われるべきであるのかということについての洞察をもたらす真理を知る師である。彼が遠くを見通すにせよそうでないにせよ、彼は望まれる真理のみを見るべきである。もし人が遠く広く見るということのみにもとづいて権威であるならば、遠く広く見渡すことという点で優れているハゲワシでも崇めていればよかろう。(328頁)