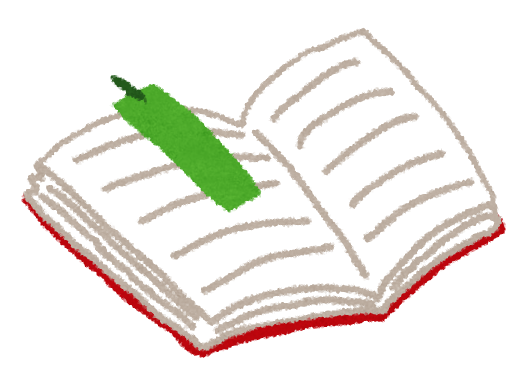著:ジャン=ノエル・ロベール/訳:今枝由郎/講談社選書メチエ
著:ジャン=ノエル・ロベール/訳:今枝由郎/講談社選書メチエ
山形県酒田市で、ボードゲームカフェを営むフランス人ピエールさんは、空き時間を利用して観光ガイドも務めている。そのピエールさんの車に乗せてもらい、二体の即身仏を祀る海向寺(真言宗智山派)や日本海を一望できる日和山公園などを案内してもらった。地中海沿岸の出身であるピエールさんがフランス語なまりで説明すると、かつて北前船で栄えた東北の港町にいるのに、いつの間にか南フランスのような気がしてくるから不思議だ。
本書はフランス人がフランス人のために書いた仏教の概説書を翻訳したものである。原文タイトルは「仏教小史(Petite histoire du Bouddhisme)」である。ヨーロッパではフランスの仏教徒が最も多く、寺院や仏教センターがいくつもあって、若い世代からも肯定的なイメージを持たれているが、その中身は「ライトメニュー禅」であり、実際は時代・地域によって実に多様であることを示したかったという。お釈迦様の誕生から、言語が全く異なるアジア一帯、さらに欧米までどのように伝播したのかを、新鮮な言葉遣いで説いており、仏教に慣れ親しんだ日本人にも、新しい発見をもたらす。
日本だけでなく、中国、朝鮮半島、ウイグル、モンゴル、チベット、東南アジアと幅広く仏教が伝わった経緯が紹介されており、またキリスト教やイスラム教との対比や歴史的な影響にも触れられている。評者が興味深いと思ったのは次のトピックである。
- ブッダは、カトリック教会の聖人のひとりとして崇められるようになった
- 般若波羅蜜は、同時代にギリシャで興ったグノーシス派のソフィア(知恵)と類似
- イエズス会宣教師が十八世紀、チベット語で書いた仏教批判書がある
- パーリ語はブッダ自信が話した言葉でないことは確実で、すでに翻訳語である
- パーリ語「スッタ」は、サンスクリット語「スートラ(経)」ではなくて「スークタ(善言)」説
- 訳経僧の鳩摩羅什は、中国人に半ば誘拐されて長安に連れてこられた
- チベット仏教で論理学や文法など基礎から学ぶのは、密教への反動
- 大乗仏教や密教は東南アジアにも伝わっており、テーラワーダが広まったのは後代になってから
- 韓国・曹渓宗の開祖は中国に渡る途中で悟りを開いて引き返した
- 日本天台宗は真言宗と比べて「魔術的要素」にかけており、その欠如を補うために台密を取り入れた
禅宗や道元禅師については数行の記述にとどまるが、鎌倉仏教について次のようにまとめられているのは考えさせられる。念仏も坐禅も「仏教の単純化」と一括りにされるのは、それこそ単純すぎると思うかもしれないが、日本全国津々浦々に寺院が広まり、現在まで存続しているのはこの「単純化」によるところが大きいのかもしれない。中国の禅仏教についても、雑多で相互にくいちがう大蔵経の教義からの抜本的断絶と捉えられている。
こうした潮流の全てに共通しているのは、膨大な大蔵経に説かれている極めて複雑な教義、実践、儀式の抜本的単純化である。実際のところ、大蔵経全体を読んだと自慢できるのはほんの一握りの僧だけである。民衆、貴族、武士に自らが実際に、そして有効的に仏教を実践しているという気持ちを抱かせたことが、こうした単純化された教えが、さまざまな階級に受け入れられ、普及した理由である。(一一五頁)
そもそも著者は日本語や中国語や学び、日本仏教を研究してきた研究者で、「極東」である日本を一つの終着点とみている。インドから中国・朝鮮を経て日本に至るまで仏教は変容してきたが、日本に伝来してからもさらに多くの変化を遂げた。その一宗派にいる我々が、「これが正伝の仏法だから」といって伝来の歴史や多様な仏教の有り様を知らないでいることは、結局自宗の理解をも遠ざけてしまうだろう。訳者の今枝氏は解説で著者の「仏教は多様性を含んだ宗教であり、ある事柄に関して仏教ではこうであると決定的に断定することが非常に難しい」という言葉を引用し、「この鳥瞰的な視点こそが、従来の日本仏教に、明治以降の仏教研究者に、そして現代の日本人仏教徒に致命的に欠如しているものである」と述べている。観光でも仏教でも、日本の良さに気づくには、いつも外部からの視点が必要である。