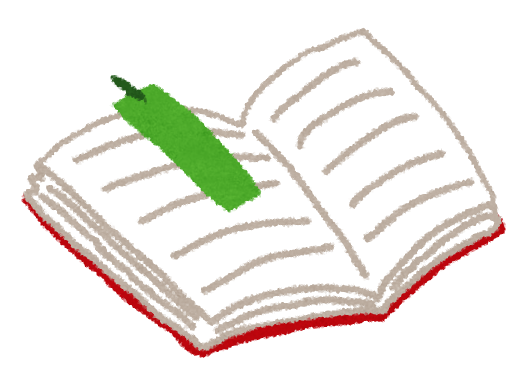学生時代にインド仏教の論書を読んでいるとき、「ここから先は、修行しないとわからない」と書いてあるのを見てガッカリしたことがある。バラモン教であれば、論理立てて読解できればスッキリする。仏教でも初期の経典ならば、常識的に理解できる内容である。しかし大乗経典、さらに禅籍となると、机上で辞書をいくら引いても、先生に教えを請うても全くわからないことが多い。あるいはわかったつもりになっても、その理解が大きく覆される不安は常にある。あれから三十年も経ち、大乗経典にも禅籍にも親しむようになり、その一部がふと腑に落ちるようなこともようやく出てきたが、全体的にしっくり来るようなことは、一生かかってもあるものだろうか。
道元禅についてはなおさらである。「無分別」や「非思量」とはどのようなものであるか、実際に坐禅をしてすら、なかなかしっくりこないのだから、ただテキストを読んだだけでは、何となくわかった気になっているだけではないかと思ってしまう。師匠や先輩方からの指導や問答が伝統的に行われているのも、独学の難しさを物語るものであろう。
本書もそんな理解の一助となる。今年七十五歳を迎える唯識思想の大家が、この年になってまとめられた道元禅師の思想で、書物の半分ぐらいを引用で占め(テーマ別の引用集としても有用である)、生死、修証、言語、時間、坐禅というテーマに分けて注意深く考察している。全体を通して「脱落即現成」、すなわち坐禅という主観的な体験と、真如という客観的な世界をひとつのものとして統合する道筋を説く。坐禅によって仏の世界を見るのではなくて、自分自身が仏の世界の一部になるのである。
生に愛着することもなく、ただ生そのものを生き抜く。死を恐怖することもなく、ただ死を死に抜く。そこに、生死に出入する自由、生死を使い得る自由が成立すると示している。それがすでに仏性とともにある自己のあるべきあり方なのである。(61頁)
自己が自己をならい、自己になり尽くす(透体脱落)ときに、むしろ自己の根源としての仏性に出会う。それは、対象的にではなく、自己が自己をならって自己を忘れることにおいてである。しかしこのとき、かけがえのない自己を失うのではありえない。(207頁)
これは個人の神秘的体験ではない。個人の坐禅が世界全体に影響が及ぼすことを、筆者は「修証共同体」と名付ける。初心のうちから、他とともに、他のために、他に開かれた修行(「為他の志気を衝天せしむるなり」)が推奨され、修行と悟りも他と内的につながっている(「浄信一現するとき、自他同じく転ぜられるなり」)。坐禅は、独りでしていても独りではない。また、この初心さえ忘れなければ、礼拝も読経も、日常生活も全て修行となる。「立っている時も、歩いている時も、坐っている時も、あるいは横になっていても眠っていない限り、この慈悲の念をしっかり保つこと」(スッタ・ニパータ)である。たとえ深山幽谷に閑居して一個半箇の弟子に専念しようとも、大乗仏教の理念を外れるものではない。それどころか、真摯に衆生の利益を祈るものであろう。
我々の行持が諸仏の行持を支え、諸仏の行持が我々を支える。むしろこの行事の交流の世界にあって、その行持の功徳が今・ここに結ばれるところに個があるのである。しかもそこにも道環と呼ばれるべき事態があるという。故に行持道環は、縦に発心・修行・菩提・涅槃をめぐると同時に、横に諸仏初祖に、諸々の凡夫・有情をめぐる。あるいは逆に、縦にめぐる環と横にめぐる環の交点に自己があるのである。(111頁)
鈴木大拙は、『正法眼蔵』で道元が「雪上加霜、土上添泥の落草談を千言万語」したために、彼の子孫が苦しめられ迷わされたと語っている(終章「鈴木大拙の道元観」)。しかし『正法眼蔵』は凡夫の理解を超越した「仏祖の理会路」で語られており、絶対に対象化できない真如のあり方をあえて対象化する試みなのである。またそれは「仏教はすなわち教仏なり」「菩提語にして語菩提」というように、真如を表現するのではなく、真如そのものを現前させることになる。「荒磯の 波も得よせぬ 高岩に かきもつくべき 法ならばこそ」とは、経典や『正法眼蔵』が我々を迷わせるものではなく、導いてくれるものであることを示しているだろう。
「道元の坐禅観」では、『永平広録』に収録された上堂のお示しをもとに、晩年さらに坐禅に打ち込んでいった様子を描く。数息観、不浄観、自調の心、涅槃を求むる趣といった他宗派の坐禅を排して、身心脱落の坐禅に励むことをひたすらに勧める。宋からの帰国当初、「坐禅をして身心脱落せよ」と言っていたのが、晩年は「坐禅は身心脱落なり」になったという。「身心脱落」が、ストンと何かが腑に落ちる(悟り体験)から、仏の世界を現成させることに変化しているところが興味深い。ここに『正法眼蔵』の思索が結実したともいえよう。
「ここから先は、修行しないとわからない」という領域は仏教に確かにある。しかし坐禅するだけで、その領域にすんなりと入っていけるのである。