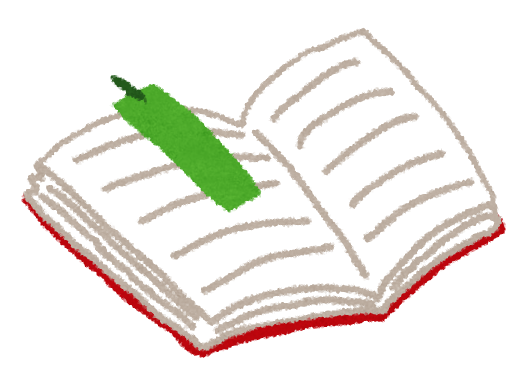プリンセスと王子様、紅一点キャラクターの扱われ方、男子部長と女子マネージャー、女子の理系選択のしづらさ、実家離れ・浪人の回避などなど、赤ちゃんから幼児、小学生、中高生、大学生と章立てして子どもに刷り込まれるジェンダーバイアスを考察。大学講義をもとにした構成で、学生の感想入り。性別役割分担意識は薄いと思っていた我が家でも、無意識にやらかしていたような気がして、一章読むたびに反省していた。
- ベビーX実験:赤ちゃんが女の子だとわかると、男性も女性も大人は人形を差し出す確率が高い。
- 青い目、茶色い目実験:クラスで茶色い目の子どもは配られた襟をつけて、失敗すると「だから茶色い目の子はだめね」と言われる。次の日は「昨日は間違っていた、本当は偉いのは茶色い目の子のほうだった」と告げられ、青い目の子に襟が渡される。そうすると、茶色い目の子たちは2日目のほうが成績が良く、青い目の子たちの成績は落ちた(最後は襟を取り、「目の色や肌の色で人を判断してよいか」聞かれて皆ノーと答えた)。
- マイクロアグレッション:マイノリティが日常的に受ける些細な差別。その場に歓迎されていないように感じたり、褒めているように見えても、積み重ねでダメージを受ける。高校・大学ではもっと強い「言葉の逆風」が未だなくならない。「女の子は17歳で学力の伸びが止まる。男の子は受験直前まで伸びる」「女性は浪人すると婚期や出産適齢期を逃す」「女の学歴に価値はない」「結婚したし、働かなくても大丈夫だね」「研究するなら子どもは諦めたほうがいい」(幸い、理系の妻はこういうことを言われたことがないそう)
- 統計的差別:個人を見ずに平均値で判断して差別する。「女性は辞めやすいから雇わない・成長機会を与えない」
- 逆選択:質の違うものを一緒に扱うと、期待に反して質の良いものが去り、質の悪いものしか残らないパラドクス。「意欲がある、または優秀な女性ほど離脱する・成長できない」
- 予言の自己成就:予言が予言自体の力で現実となる。「男女によって興味や人生観が異なると、進路選択や能力に差が出て、実際にバイアス通りの差を生む」
- ステレオタイプ脅威:ステレオタイプに気を取られてパフォーマンスが落ち、結局ステレオタイプ通りになる。「理系に進むのすごいね!」「ついていけるの?」「理系は難しいから、もう少しよく考えた方が良い」といった声掛けが「女子は理数系科目が苦手」というステレオタイプを喚起させ、学習意欲が低下して、本当に苦手になる
- クリティカル・マス:集団の中で、組織文化や意思決定に影響を及ぼすグループになったり個人が本来の実力を発揮したりするための分岐点となる比率。国際機関や各国政府機関は「30%」を重視
「女性の透明化・商品化がはびこるキャンパス」では、女性比率2割にとどまる東京大学の現在が紹介されている。ゼミ後のお茶の洗い物を女子学生が買ってでなくてはならないこと、進路について話す時、女子学生は結婚の意志があるか聞かれること、指導教員がゼミ中に「研究をやるのは女性にモテるため」という趣旨の発言をしたこと、男子学生が大っぴらに女子学生の容姿や性的な事柄について品定めするような発言をしても当然にゆるされるような雰囲気だったこと・・・声を上げる学生が増えているのは確からしいが、いびつな男女比という構造的な問題の中、ジェンダー不平等が次世代に再生産されていく構図が垣間見えて空恐ろしさを感じた。