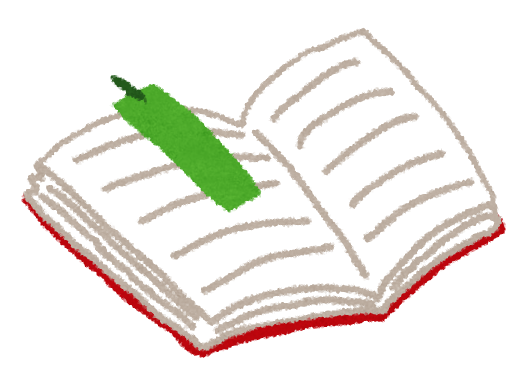八万四千の法門ともいわれ、無尽誓願学なる仏教思想をこの1冊で「全容解明」とは、さすがに大上段に構えすぎではないかと思うが、読んでみると現代的な「凡夫」の視点からわかりやすく初期経典を読み解いている。「無常」や「因果」はお坊さんが得意気に語るようなものではなくあくまで世間の常識であり、その先にある十二因縁・苦・非我の教えの核心は「自他分離」から「自他融合」への移行であるというのが主旨。
「自他分離」とは何か。私たちは物心がついたときから、自己と世界が別物であり、「わたし」がそれだけで存在するかのように思い込み、自己中心的な欲望を募らせている。これが「自他分離」で、その元となる自己を形成する力が「サンカーラ(行)」である。五蘊(色・受・想・行・識)の四番目だが、「諸『行』無常」というように五蘊の中でまっ先に問題になるものであり、苦しみの根源として滅することが推奨されている。
「サンカーラ」とはどうやら、人類の長い歴史の中で培われてきた言語・文化・社会習慣を指すようだが、個人のアイデンティティにも関わる。例えば「私は男/女/その他である」という性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は近年、トランスジェンダーなどさまざまなあり方が知られるようになり、どんなあり方であれ配慮・尊重することになっている。確かにアイデンティティはある意味、苦しみのもとになっているといえなくもない。しかしそのアイデンティティの根源を滅してしまったら、「私は男である」「私は僧侶である」「私は日本人である」というような認識が宙に浮いてしまい、記憶喪失のようになってしまわないだろうか? 他者もあらゆる属性を失ってマシュマロマン(『ゴーストバスターズ』より)みたいにしか見えなくなるのではないだろうか?
そんな心配はないようだ。筆者によれば、「サンカーラ」を静めても自他の区別は残り、「自他融合」の欲望=慈悲が現れてくるという。そして死を自然現象として受け入れられるようになり、苦しみがなくなり、心底からの安堵感が得られる。その境地になっても、ブッダが成道後四十年以上にわたって説法の人生を送り、道元禅師が最期まで『正法眼蔵』の筆を執ったように、他者への慈悲の心で教えを説き続けることはできる。
瞑想は、幸か不幸か、因果というか、ことばのない状態を実現できます。ところが、瞑想から出ると再びことばのある状態にもどります。すると修行が後退しているように感じられるので、またことばのない状態を作り出そうとします。このくり返しです。何も得るものはありません。真理を追求しようとする人々はこの罠にかかりやすいように思われます。〔届くことのない〕真理に到達することを目的としているからです。苦しみを解決したい人々はこの罠にかかりにくいように思われます。真理に到達することが目的ではないからです。(85ページ「縁起その先へ」)
このような理由から、坐禅はことばのない状態を実現するために行うのではなく、「サンカーラ」を静めて「自他融合」を進め、自己ですら思い通りにならない苦しみを克服するためのものということになる。「『考えないこと』が仏教の究極であり、それが苦しみから救う方法である、と本気で考えている仏教者もいます。そのようなことを『考えない』でいただきたい」「いまだに、『坐っていることが悟りである』、『坐禅することに意味はない』などの言説がまかり通っている」とも筆者は述べている。
仏教が目指してきた「無我」「無分別」「無欲」は決して退行ではなく、「自他融合」の自己を基盤とする新しい境地への成長であり、それぞれ「超我」「超分別」「超欲望」と呼ばれる。特に「超分別」は「智慧」に換言され、理性を捨てることではなく更に磨いて質を高めることである。さもなければ、戦時中に多くの禅者が「分別」なく天皇や国のために戦死することを礼賛した過ちが繰り返されてしまうという。戦時中に限ったことではなく、現代においても無自覚な毎日を送ることが「無我の境地」では決してない。「生死は事大にして、無常は迅速なり。各宜しく覚醒すべし、慎んで放逸すること勿れ」である。
序章で道元禅師の次の言葉が引用されている。無常を知った上で、そこからどのように行動するかを問うている点で、道元禅師はブッダに近いと評価している。「自他融合」への成長という方向性は、大乗仏教、そして曹洞禅にも通じる。僧侶という立場で「全容解明」するのは私たちひとりひとりである。
龍樹祖師の曰く、ただ世間の生滅無常を観ずるの心もまた菩提心と名づく。しかればすなわちしばらく此心に依るは菩提心たるべき者か。まことにそれ無常を観ずるの時、吾我の心生ぜず、名利の念起こらず、時光のはなはだ速やかなることを恐怖す(『学道用心集』)。