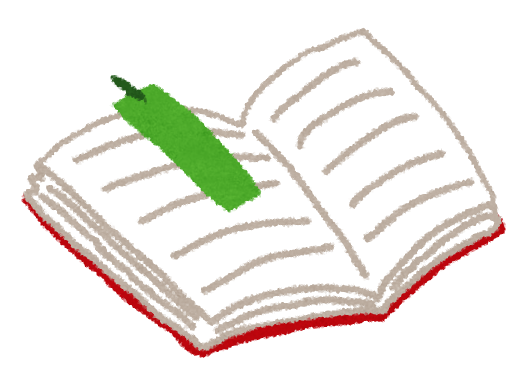短大の小論文で「〇〇について考えてみたい」から始まって「〇〇は大事だと思った」という文章を書く学生が結構おり、結論、3つの理由、結論の再説という5段落形式を指導するようになった。前者は本書で言うところの「社会/感想文」、私が指導しているのは「経済/エッセイ」という作文の型で、一概に悪いとはいえないみたい。
1.経済/エッセイ(アメリカ):効率性を重視。主張→3つの根拠→主張の言い換え
2.政治/ディセルタシオン(フランス):十分な検討を重視。問題提起→過去の見解の総合→新しい問い
3.法技術/エンシャー(イラン):不変の真理を重視。比喩→主題の説明→詩や聖典の引用
4.社会/感想文(日本):共感を重視。最初の考え→体験→自分の変化
3は引導法語の書き方と同じだなぁと感心。4について、作文コンテストで新聞やテレビの見聞よりも当事者の体験が書かれていると評価が上がるのにも納得した。4は他の思考法から見ると、意見と事実が明確に分けられていない、常識をなぞっているだけ、狭い自分に縛られているというも欠点もあるというが、日本では間主観と道徳の涵養に役立ってきたことも事実。落とした財布が高い確率で返ってくるのは、感想文文化の賜物と言えるかもしれない。
生成AIにより1は簡単に作れるようになったため、生成AIには作れない当事者の体験を小論文に組み込むように指導している。経済の論理的思考で日常体験を根拠にするのは過度の一般化になってしまうが、主張を説得的に伝えるレトリックとしてはアリなのではないかと思う。ハイブリッドな思考法を心がけてみたい。