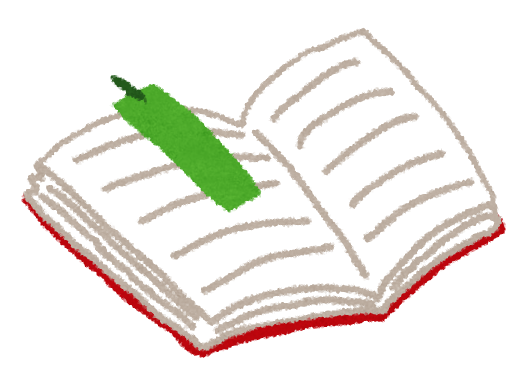この2人の特徴的な鎌倉祖師を対比する書籍はこれまでも数多く出版されているが、この本を選んだのはいわゆる「著者買い」である。平岡氏には『〈業〉とは何か』の緻密な研究や、お釈迦様の降誕や初転法輪を伝える『マハーヴァストゥ』、「黒白業」(善業と悪業は相殺しない)が説かれた説話集『ディヴィヤ・アヴァダーナ』の全訳があり、正確さとわかりやすさを両立した解説を私は何度も読み返している。その平岡氏の道元禅師論はどんなものか、読んでみたいと思った。期待に違わず、最新の研究成果に基づき、また親鸞上人との対比によって、新しい視点を提供している。
親鸞上人と道元禅師には確かに対照的な考え方が多い。絶対他力と修証一等、非僧非俗と出家至上主義、同朋同行と師資相承、一見対立するように見えるが、その根底にあるのはあまねく衆生を救おうとする大乗の理念である。「一箇半箇の接得」は「たとえ一人でもよいから、勝れた弟子を育てること」と一般的に理解されているが、「一箇半箇までも漏らさず接得する」=対象を限定せず万人を救うという新しい解釈を紹介している。出家者は仏の世界と衆生の世界を法会によって結ぶ役割を担うという。
よく言われる「親鸞仏教は他力、道元仏教は自力」についても、「自己をわするるというは、万法に証せらるるなり」「仏のかたよりおこなわれて、これにしたがひもてゆくとき」という有名な一句から、道元仏教を「他力を基盤にした自力」「他力の働きを前提に自力の修行が成立」と表現する。そもそも仏教はブッダの時代から「諸法がブッダに顕現する」というように、悟りの基盤は他力であり、法が主で仏が従であった。宗教全体で見ても、自己中心的な意味での自力的宗教はない。「宗教は我々にとって何のためにあるか」という問いの立て方は適切でなく、「人間を超えた存在にとって、我々のほうがどうあるべきか」という問いが宗教の本質であるという。
こうして、相対化された吾我は無我として再生し、閉じていた自己から他者に開かれた自己として本来的な相互依存(縁起)の関係性を回復する。そこでは自己と他者とが融通無礙に融合し、本来の全体性を取り戻す。こう考えれば、逆説的だが、中心から周囲に場所を移動し無我を自覚することで、かえって「我」の主体性が発揮される。吾我が徹底的に否定され「無」に徹したところに、真実の「我」が生き生きと動き出す。これが道元の考える「無我」だ。(208頁)
仏教は諸法無我を説きつつ、輪廻(死後の存続)も認め、一体何が存続するのかという批判をつきつけられてきた。しかしこのように執着に囚われた閉鎖的な「我」と、縁起する世界の中ではたらく開放的な「我」が別物であると考えれば、この問題は解決するのではないだろうか。「身已に私に非ず」とは、自身が自他の境界を超えて、世界の一部であると認識できたとき、逆説的に「受け難き人身」「他は是れ吾にあらず」という菩提心が生まれる。この自己変革は、できたら終わりではなくて磨き続けなければならない。
この道元禅の修行の継続を、石井(清純氏)はダイナモライト、つまりダイナモ(たとえば、昔の自転車についていた発電機)を回し続けなければ、ライトは消えてしまうことで説明するが、私は竹原ピストルの歌「きーぷ、うぉーきんぐ!!」(映画『BLUE/ブルー』の主題歌)で説明しよう。その一節に「もはや足跡を残したいわけじゃない。でも足跡を鳴らしていたいんだ」とある。足跡を残すのは過去のこと、一方「足跡を鳴らしていたい」は「現在という瞬間の連続」だ。道元禅の核心をついた歌詞ではないか。(194頁)
このように行住坐臥、一瞬たりとも怠ることなく修行に打ち込み続けることは容易ではないが、せめて昔の旅館にあったコイン式のテレビ(お金を入れないと一定時間で止まる)のように、坐禅なり礼拝なり、経典祖録の学習なり、定期的に気持ちを引き締める機会はもち続けておきたいものである。
親鸞上人の人間観が「過去→現在(人は過去の悪業に拘束された、意のままにならぬ存在)」であるのに対し、道元禅師の人間観が「現在→未来(人は現在の業を変えることで未来は切り開ける存在)」だという視点の対比は興味深い。末法思想の中で「吾等が当来は仏祖ならん」と、未来に希望をもって修行に励む、その未来を私たちは生きている。その間に多くの宗侶は俗化したけれども、檀信徒に寄り添って同朋のように接することができるようになったともいえる。そうなれば非僧非俗として生きた親鸞の教えも参考になるかもしれない。
例えば『歎異抄』第十八条では、布施の金額の多寡で浄土往生に違いが出てくるという見解に対し、布施に重要なのは信心であり、その多寡はまったく問題にならないこと、このような考え方は物欲を仏法にかこつけて同朋を脅していることになると戒める。「布施というは貪らざるなり」と言っておいて自分が貪っては全く示しがつかないどころか、信心を失わせてしまう。「お寺に搾取されない」などという書籍(『墓じまい!』)が出てしまうほどに今、檀信徒の心は離れている。そこに新宗教が入り込む余地も生まれるだろう。「今生の仏法修行は、これ檀越の信心によりて成就す」というように、勝れたる友であり続けたい。