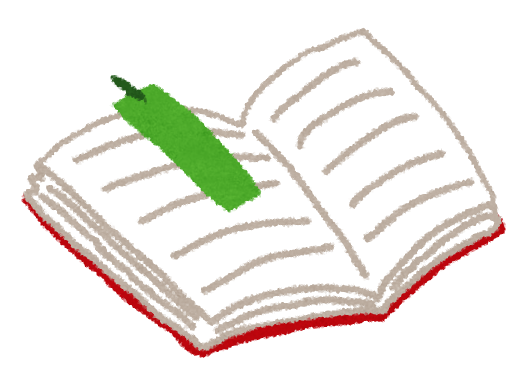著・清水俊史
ブッダは平和主義者であった、業や輪廻を否定した、カースト差別を否定した、女性差別を否定したといった見解を現代的神格化として、仏典に見られる「当時の常識」を挙げていく。
「あなたは耐えなさい。数年、数百年、数千年ものあいだ地獄で煮られたであろうその業の報いを、あなたはまさに現世で受けているのです。(中部)」
「氏姓に属する人々のうちでは、武士階級が最上である。(長部など)」
「女は怒りやすい。女は嫉妬深い。女は物惜しみする。女は愚痴である。(増支部)」
こういった記述を見て見ぬふりをして、現代的価値観に合致するところ(往々にして仏教独自の見解ではない)だけ恣意的に取り上げるのは、少なくとも学術的にはフェアでない(宗派としては、どこを取り上げるかで宗派に分かれるわけなので、仏言の取捨選択は祖師の見方に通じているかどうかというところが大事である)。
例えば第1章「ブッダとは何者だったのか」では「天上天下唯我独尊」が検討されている。「すべての存在は尊く、かけがえのない命を与えられている」と現代的に解釈することは曹洞宗でも行われているが、パーリ語原典でも「私は世間で最も優れた者である」という意味しかなく、当時の歴史的・教理的文脈からすれば当然のことであって、ブッダを崇めるための後世の創作と考える必要もないという。
なお、いわゆる「悪しき業論」をまさにお釈迦様が説いていたということは、宗教者であっても理解はしておくべきだろうと思う。その上で、現代においてどのような解釈だと通用するのか、参究していかなければならない。禅宗にはこの問題を禅問答的に乗り越える力があるはずだ。
過去の業を滅する方法は、(黒白業ではなく)善業による相殺のほかに、渇愛(煩悩)をなくして業報を生じさせないという教えは四諦十二支縁起を理解する上で大事である。無我と輪廻がどうして両立するのかという問題も、五蘊の精神的要素(受想行識)が変化しつつも相続されていくからという説明は納得しやすい。そこに真なる自己があると想定することは、ブッダが戒めた我執なのかなと思う。
「業は田であり、識は種子であり、渇愛は湿潤である。無知という障害と、渇愛という束縛とを抱く人々の識は、劣った世界に安住する。このように、未来に再有の生起がある。(増支部)」
批判されている仏教学者の再反論も俟たなければいけないが、本書に述べられていることがその通りだとすれば(納得感はある)、仏教の常識も変わる可能性がある。あとがきで著者は、東大の馬場教授の説を批判して出版妨害などの圧力を受けたという(馬場教授は事実無根と反論)。どちらにも言い分があるようだが、「生産的な協力と健全な競争」のもと、この分野の研究が発展することを祈りたい。