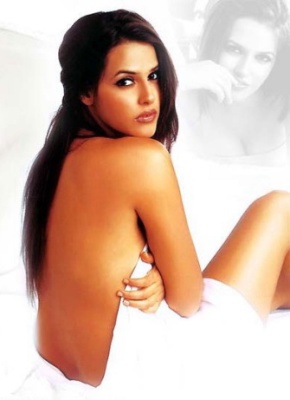 Julie(ジュリー)
Julie(ジュリー)
〈あらすじ〉
ムンバイの高級マンションで朝寝坊している女。夜からつけっぱなしのテレビに「最も結婚したい男」としてシャンデリア財閥の御曹司スニルがインタビューを受けていた。「私には結婚したい女の人がいます。」そのインタビューを見た彼女は急いでテレビ局に向かう。
彼女の名はジュリー。職業はコールガール。陽気な行楽地ゴアで育った彼女はクリスチャンの村娘で、地元で漁業を営む恋人との結婚を夢見ていた。大物になりたいとマンガロールに行く恋人に、ジュリーは体を許す。しばらく後、成功して帰ってきた恋人に喜んで会いに行ったジュリーは、恋人が別の婚約者を連れてきているのを見る。傷心したジュリーは、もうゴアにいられないと友人を頼ってムンバイに行った。
ムンバイでは建設会社の秘書として採用され、そこで働くデザイナーが親切にしてくれた。やがてジュリーはそのデザイナーと恋に落ち、体を許した。しかしその幸せな生活もつかの間、デザイナーは社長に、ジュリーを夜のお伴として送ったのだった。それを知ったジュリーは怒ってデザイナーのところに行くが、「お前が会社に採用されたのは能力なんかじゃない。体なんだよ。どうしてそれをわからないのか」と言われる。
すっかり意欲をなくしたジュリーは、コールガール斡旋業のおばちゃんと会う。おばちゃんに「みんなが求めているのは体だけなのよ」と言われ、ジュリーはコールガールの道を選んだのだった。
ある夜、ホテルの前で引ったくりにあったジュリーは、そこを通りかかった男の車に乗って家に帰る。しかし鍵も持っておらず家に入ることができない。結局朝まで外で過ごすことになるが、その男こそスニルであった。彼は海岸で朝日を浴びながらはしゃぐジュリーを見て恋をする。
さて、テレビ局に向かった彼女は自分の職業を明かし、同じインタビュー番組に出ることを申し出る。「私はジュリー。売春婦よ」という番組宣伝は評判を呼び、インタビュー当日はたくさんの人が街頭のテレビに集まった。
インタビューは彼女のこれまでを全て話し、シャンデリア財閥の御曹司の話にまで至った。マスコミは格好のスキャンダルができたと大喜び、シャンデリアグループはひっきりなしに電話の対応に追われ始める。「売春婦だから、私は彼と結婚できない」と泣き落ちるジュリー。
そこにスニルがスタジオに登場。「売春婦だろうと、僕が結婚したい気持ちは変わらない」とジュリーを抱きしめるスニル。これまで批判調だった会場の人も、街頭のテレビに集まっていた人たちも、そしてテレビを見ていたスニルの家族も、二人に惜しみない拍手を送るのだった。
〈感想〉
お色気ものの俗な映画だろうと思って見ていなかったが、ロングヒットが続いている。新聞でも「貧しさから仕方なくではなく、自ら職業として売春婦を選んだ女性の自立心」などの評論が載っていたので見ることにした。お色気シーンを期待していかなかったかといえばウソになるが、そういうシーンはほとんどない。むしろ先日見た「ガーヤブ」の方がずっと多いぐらいだ。
最後に二人に拍手が送られるシーンが感動的だったのは、売春婦という職業に就いている人を、みんなが同じ人として見たと感じたからである。もちろん人によっては、可愛そうな子犬を拾った大金持ちの心の広さに拍手を送ったのかもしれないし、あるいはゴアの村娘が幾多の困難を経て幸せをつかんだというシンデレラストーリーに拍手を送ったのかもしれない。しかし私は、職業の貴賤を問わないという立場を実現したことに感動を覚えた。
世間ではあまり知られていないかもしれないが、お坊さんの宴会で酌婦(酒注ぎと話し相手)が呼ばれることがある。酌婦がいないと若いお坊さんが注ぎに回らなければならず、落ち着いて飲み食いできないという配慮と、男だけでは盛り上がらないという色気からそういうことをしているのだと思う。教養もなく、タバコを吸いながら下品な話しかできない酌婦を、私は半ば軽蔑していた。
しかしある宴会で、アルバイトで酌婦をしている音大生と会った。彼女の勉強の話を興味深く聞きながら、「どうしてこんな仕事を……」と言いかけて、しまったと思った。この職業が賤しいとするならば、彼女たちのアイデンティティは何なんだろう。しかし彼女たちの前で「職業の貴賤を私は問わない」と宣言することもまた、その職業が賤しいという世間の観念を事実上追認していることになってしまう。それは軽蔑すべきただの自己満足でしかない。口だけで差別を乗り越えることは決してできず、ただ行動で示すしかないということ、そしてそれは容易ではないことがそのとき分かったのである。
愛という強力な力を背景に、職業に貴賤がないことを求婚という行動で示したスニル。そして自分を売春婦にしてしまった過去に固執せずスニルの愛に応えたジュリー。いつだって愛というものは、そういうものであるべきではないだろうか。