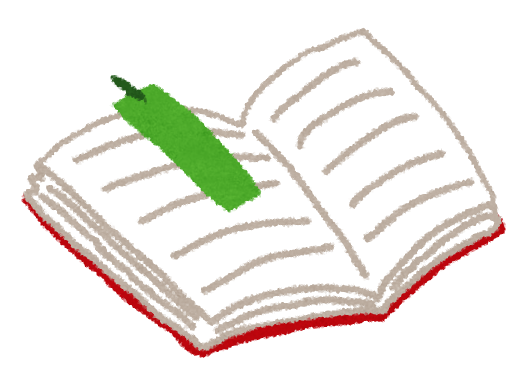『正法眼蔵・観音』において「観音菩薩はたくさんの手眼を用いてどうするのか」「人が夜間に手を後ろに回して枕を手探りするようなものだ」(如人夜間背手摸枕子)という禅問答が出てくる。観音菩薩が慈悲の心をもって差し伸べる手は、衆生に向けられているのではなく、自己の正体を求めるため自分自身に向けられているという。利他行は「彼が報謝を求めず、唯単えに利行に催おさるる」ものであっても、自己を見つめ直し、仏になるための修行という点では坐禅と変わることがない。「常に大慈大悲に住して坐禅無量の功徳、一切衆生に回向せよ」(『坐禅用心記』)とは、坐禅と利他行のどちらが先ということではなく、どちらにおいても自己のうちにある慈悲心を保ち続けることの大切さを説いているといえよう。
本書は、価値観が多様化し、「あなたが大切にしているものは、私の大切にしているものと異なる」現代において、善意が空回りすることが増える中で、ケアや利他の可能性について、ウィトゲンシュタインから『鬼滅の刃』までを題材に考える。「ありがた迷惑」「小さな親切大きなお世話」「情けが仇」「口は災いの元」になることを恐れて、「何もしない、何も言わない、できるだけ人と関わらないのが無難」になりがちな今日このごろ、視点を変えて自分にできることが見つかるように思われる。
本書のキーワードとなる利他・ケア・傷は次のように定義される。
利他:自分の大切にしているものよりも、その他者の大切にしているものの方を優先すること(自己<他者)
ケア:その他者の大切にしているものを共に大切にすること(自己=他者)
傷:大切にしているものを大切にされなかった/大切にできなかった時に起こる心の動きおよびその記憶
ケアは同事行といってもよいだろう。「自をして佗に同ぜしむる」には、相手が大切にしている(のに、大切にされなかった)ものを知らなければならない。「しかしそれは相手の心のうちに隠れているからわからない」という考えを、筆者はウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」でいえば誤解であるといい、相手が経験した無数の出来事と行為のつながり(「星座」)が見通せず、どのように応答したらよいかわからないだけだという。ある言動をフォーカスするのではなく、視野を広げてその背景(「物語」)を知り、その続きを共に作り出すことによって、相手が何を大切にしていたのかが、後からわかってくる。この「その人だけの物語を共に作り出す」ことが、ケアとなる。
ケアはあくまで相手主体であるために、善意の空回りはない。先入観を排してその人とひたすら向き合い、相手の求めることが見えてきたら、それに応じる。これによって相手の「物語」が更新され、出来事の意味が切り替わり、過去をプラスに解釈できるようになったとき、ケアが成就する。
「あなたは何も間違っていない」それを示すこと。これがケアの本質です。それがバフ(プラスの効果を付与するもの)であり、祝福です。どれほど逸脱的に見える行為にも、それがその人にとって大切な行為なのかもしれないという、判断の留保が他者理解の第一歩である。その眼差しの後に、やさしさの振る舞いが顕れる。(214頁)
「あなたは間違っている。それゆえ、私があなたを導こう」という姿勢は、叱る側つまりコントロールしようとしている側からすると、「善い行い」になります。自分はいま善いことをしているという自己認識を容易く得られるのです。/これに対し、本当の意味での倫理的な言葉はこうではないでしょうか。「私は間違っているかもしれない。だからあなたに導いてほしい」ここに「強制」はありません。自らが認識し、自らが選択したことです。そして、この希求の念を汲んで、これに応じること。それがケアであるはずです。「待つ」というのはこういうことです。(226~227頁)
ケアの実践を考えた場合、「傾聴」がこれにあたるだろう。傾聴のコツは「分析しない・批判しない・助言しない」だと言われる。何か相談をされたとき、内容を勝手に整理したりせずそのままの気持ちを受け止め、相手が自分のことを棚に上げていると思っても批判せずに共感し、安易にアドバイスをしたくなる気持ちを抑えて最後まで聴く。「話を聴いてもらっただけでスッキリしました」という人が多いのは、話しているうちに、自分の中にある「物語」が何らかの形で更新されるからではないだろうか。
その先にある利他は、自己犠牲ではないと筆者は言う。なぜなら、「利佗を先とせば自らが利省かぬべし」と思っていた自分は、相手の物語を受け入れることで「利行は一法なり、普く自佗を利するなり」と思う人間に自己変容しているからである。利他は(社会のルールとしての)道徳ではないどころか、ときに道徳と対立する愚行でなければならず、勇気が要ることなのに得るものはないとわかっていて行うことである。そのとき私たちは自由であり、「自分の人生を生きている実感」が得られるという。
誰かのために大切な何かを手放すことで私が変わる。そうあるべきと命じられたものを破り、自らが言語ゲームを選び直すこと。利他とはそのように構造化されている。それは決して自己犠牲ではありません。なぜなら、それまでであれば単なる犠牲として捉えていた「私」自身が変容してしまうのだから。もはやそれを自己犠牲と規定できる私はいない。自己犠牲とは、私が変わらないままで何かを手放すことです。(240頁)
よく、「社会に出ると正解のない問題に取り組まなければならない」という言い方がされますが、これは不正確ですし、不誠実です。正解はあるのです。それは権威者が事前に用意した、確固たる模範解答ではありません。そうではなく、私の行為が「正解だったことになる」という形の、遡及的・事後的な正解はちゃんとあり得るのです。正解を制作する。生きるとは、そんな創造的行為の積み重ねのことです。(217~218頁)
利他の例として『沈黙』で踏み絵を踏むロドリゴと、『楢山節考』で姥捨て山に置いてきた母のもとに一言伝えるためだけに戻る辰平が挙げられ、これらは「傷を負うことになる未来の自分」への利他行であると解する。他者の傷をケアするため、あるいはケアできなかったことを後悔する人生にしないため、誰かから非難され、信用を失うことも承知の上で、後から「正解だったことになる」ことを信じて他者に向き合い、自己を変容させること、それが「利行に催おさるる」ということだろう。容易なことではないが、相手がかつて何を大切にされなかったのか、何を大切にできなかったのかという視点から始める時、自分のするべきことも自ずと見えてくるように思われる。
冒頭の禅問答でいうと、観音菩薩の三十三化身は方便ではなく、相手ひとりひとりに合わせてその都度自己変容した結果ともいえる。自己変容によって執着を放下し、心身脱落していくならば、利他がひとつ成就するたびに「生死を離れ、仏となる」ことができる。「自未得度先度他」こそが即ち涅槃なのである。