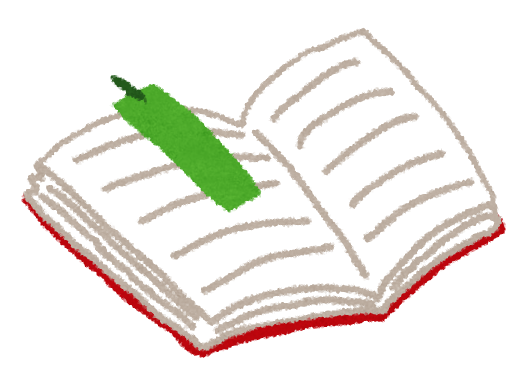「マインドフルネス」や「ヴィパッサナー瞑想」は人口に膾炙して久しいが、宗門では坐禅とは根本的に異なるものと捉えつつ、坐禅指導上、参考にできるところは学ぶというかたちで一定の距離を取ってきた。しかしヴィパッサナー瞑想を標榜する宗教団体に住職が傾倒し、護持会が問題視して、宗務所に対応を願い出るという事件が起こるに及び、「マインドフルネスは仏教でも禅でもない」と注意を喚起するに至った。宗侶や寺族が余道に帰依してしまうことが諌められているのであり、それをわきまえていれば既存の諸活動が問題になることはないとはいうものの、新興宗教に対するような警戒感が広まっているのも確かだ。
ヴィパッサナー瞑想は南伝の上座部仏教、坐禅は北伝の大乗仏教に伝わってきたものだから伝統的に大きく異なり、簡単に比較することはできない。「身心の観察」か「身心の脱落」という区別の仕方もあるようだが、そもそも「身心」の捉え方からして異なる。ましてや優劣を論じたり、批判したりするのは何も益することがないだろう。
本書はマインドフルネスに対する理解を深めるために、多分野からのアプローチとして編まれているが、「仏典」には南伝のパーリ仏典だけでなく、中国天台宗の『摩訶止観』(六世紀)やそこで引用されるインド招来の『坐禅三昧経』や『大智度論』(ともに五世紀、鳩摩羅什が翻訳)、現存最古の清規である『禅苑清規』(1103年)、日本の法語集『夢中問答集』(1344年)といった北伝の仏典も紹介されている。特に本書の大きなテーマである「負の反応とその対処法」に関する考察について、北伝の仏典が伝えてきたことは、今日の坐禅にとっても有益だと思う。
『摩訶止観』に説かれる「負の反応とその対処法」とは、次のようなものである(第一部第二章「止観の分類とマイナスの反応への対処法」)。
- 貪欲(特に色欲)が強い人 ― 不浄観(身体が汚れに満ちているという観察)
- 瞋恚が激しい人 ― 慈悲観(幸せの念願を身近な人から疎遠な人へ広げていくこと)
- 愚痴すなわち道理を理解できない人 ― 十二因縁観(苦しみの原因を無明へとたどっていくこと)・界分別観(身心を分解してどれも私でないと知ること)
- 貪瞋痴を等しい割合でもっている人 ― 観想念仏(仏を心の中に思い浮かべること)
- あれこれ考えてしまう人 ― 入息出息観(呼吸に意識を集中すること)
- 過去の体験を思い出してしまう人 ― 破法遍(過去のものはすでに実在せず、心が作り出したものに過ぎないと観ること)
- 経験していない幻覚が現れる人 ― 強心抵捍(強い意志で拒絶すること)
身心脱落や修証一等といっても簡単には達成できないことは確かで、さまざまな負の反応は私たちの坐禅中にもよく起こる。伝統的な対処法を知っておき、負の反応を解消した上で無想禅を実現することは、自身の坐禅においても、坐禅指導においても役に立つだろう。あれこれ考えてしまうことと、過去の体験を思い出してしまうことは特に起こりやすいが、その対処法である「入息出息観」と「破法遍」は単に負の反応を解消するだけでなく、そこを入口として即心是仏や一切皆空の境地につながっていくのではないだろうか。
『禅苑清規』ではこの対処法について簡潔に「正念を保ち続けること」というくらいだが、『夢中問答集』では負の反応を内的なものと外的なものに分け、内的なものの例として異様な道心と怠け心、指導者への盲信と不信を挙げ、他人より勝れていると思い込む高慢の心と、自我の利益になるものに執着する有所得の心が原因であるいう(第一部第三章「中世禅宗における身心の観察」)。道心も信頼も極端ではかえって害になる。慢心と執着を手放して、中道を目指す。容易なことではないが、極端に偏らないように心がけたい。
もしも琴の弦が張りすぎてもいないし、緩やかすぎてもいないで、釣り合いの取れた度合いをたもっているならば、そのとき琴は音声こころよく、妙なるひびきを発する。それと同様に、あまりに緊張して努力しすぎるならば、こころが昂ぶることになり、また努力しないであまりにもだらけているならば怠惰となる。それ故に汝は釣り合いのとれた努力をせよ。(『マハーヴァッガ』)
なお、本書では心理学と脳科学からもそれぞれの専門家が、雑念が起こって集中できない場合の対処法を考察している(第三部、第四部)。特に持戒を現代的に解釈し直し、負の反応を解消する手段として考察した第三部第三章「マインドフルネスと戒の関係」は、只管打坐と日常生活はつながっていることを考えさせられるもので興味深い。