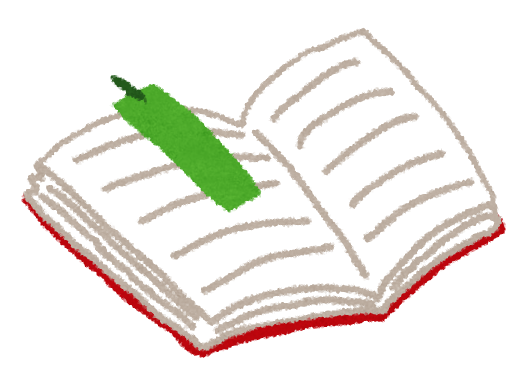コンパッションとは、「思いやり」や「慈悲」と訳され、自他を深く理解し、他者の役に立ちたいという純粋な思いのことである。宗門なら「発願利生」といってもよい。これを利他性・共感・誠実・敬意・関与という五つの要素に分析して、良い面ばかりでなく害になる面もあることを示す。著者は禅僧でもあるアメリカの人類学者。
とかく私たちは、慈悲や四摂法を説くとき、きれいごとに終始しがちである。そして聴くほうは、いい話だったということしか記憶に残らない。慈悲や四摂法を実践しようとするとさまざまな現実の壁が立ちはだかるのに、その壁の乗り越え方を伴わない話は「どうせ自分には無理だ」「それは理想論だ」と右の耳から左の耳に通り抜けてしまうだろう。
世のため人のために役立とうするあまり、独りよがりや偽善になってしまう場合(病的な利他性)。相手の悩み苦しみに寄り添おうとするあまり、自分が当事者であるかのように傷ついてしまう場合(共感疲労)。誠実に生きることを目指すあまり、至らない自分や他人に罪悪感や憤りをもってしまう場合(道徳的苦しみ)、人に敬意を強くもつあまり、意に沿わない人を裏切られたと感じて敵意をもってしまう場合(軽蔑)、全身全霊打ち込むあまり、強迫的になりやがて疲弊してしまう場合(燃え尽き)。これが本書で説かれる五つの害になる面である。刑務所や外国でのボランティア活動など豊富な経験にもとづいた実話がたくさん入っており、さらに五戒、八正道、アングリマーラ、六波羅蜜、入菩提論、チベット仏教、百丈懐海、夢中問答集など仏典からの引用にも事欠かず、仏教書といってもよいほどだ。
説法を聴く檀信徒ばかりでなく、僧侶こそ、仏典に親しめば親しむほど、志が高ければ高いほど、このような害に陥ってしまいそうである。親切のつもりがありがた迷惑になっていないだろうか。自分の評判を高めるほうに目的が移っていないだろうか。衝撃的な話を傾聴してトラウマになっていないだろうか。自分のことは棚に上げて他の僧侶を「あの人はけしからん」と陰口していないだろうか。昔あれだけ一生懸命やっていた勉強や布教を結果が出ないからと投げ出していないだろうか。おそらく誰しも多かれ少なかれ思い当たる節はあると思う。正直を言えば、筆者はどれも思い当たることばかりである。
現代では、それだったら何もしないほうが、他人とできるだけ関わらないほうがましという結論になりやすい。仏遺教経の八大人覚でも「遠離」といってしがらみを離れて独りで暮らすことを勧めているではないか。しかし大乗仏教を受け継ぐ我々にとって、慈悲の心は存在意義そのものである。本書では、たとえ失敗したとしても災い転じて福となす、泥の中から蓮の花が開くことを説く。むしろ百尺竿頭一歩を進むぐらいの勇気があったほうがよい。
これまでの理解という崖から落ちたとしても、その転落から、人生のバランスを保つことがいかに重要かを学べます。苦しみの沼にはまっても、腐った泥が蓮の滋養となることに思いいたります。海に流されたら、嵐の真っ只中であっても大海原で泳ぎ方を学びとるはずです。そうしているあいだに、生死の波のうねりに身を任せる術を心得ることもあるでしょう。その傍らには、慈悲深い菩薩である、観音菩薩の姿があるかもしれません。(36頁)
崖から落ちても立ち直れるように、GRACE(グレース)と呼ばれる、コンパッションを育てるプログラムがある。
・G(ギャザー)=集中する:息を吸って注意を集中させ、息を吐いて身体の安定を感じる
・R(リコール)=思い出す:他者を支援するという原点に立ち返る
・A(アチューン)=合わせる:自分を見つめ、相手を客観的に見る
・C(コンスィダー)=考慮する:自分のできることと相手の状況から、するべきことを冷静に判断する
・E(エンゲージ)=関与する:適切なかたちで実行し、最後に反省する
瑩山禅師は「常に大慈大悲に住して、坐禅無量の功徳を、一切衆生に回向せよ」(坐禅用心記)と示している。只管打坐といっても坐って終わりでなく、その後で一切衆生に回向するという任務が課される。それは口だけではなく、観音菩薩の慈悲を頂いて、至らぬ自分でも何かできることを見定め、小さなことから実践するということである。
自分のしたことがありがた迷惑になっていないかよく観察し、試行錯誤を繰り返す。日日三時に礼拝して、思い上がりの心を起こさないようにする。坐禅をして身心をリセットする。善悪にも多様な見方があることをわきまえ、相手にもそれなりの事情や考えがあるのではないかと慮る。同行同修の仲間同士で互いに励まし労りあう。自分でやってみて手応えがあったら、他の人にも勧めてみる。
このような道筋は、すでに仏祖が開いている。その後を愚の如く魯の如く歩いていくだけだ(これでもまだきれいごとに聞こえたらごめんなさい)。