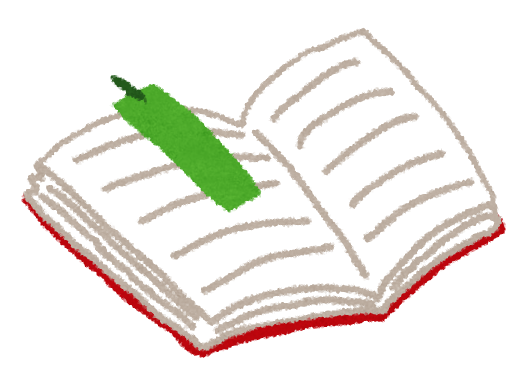学生の頃、倫理の授業で『正法眼蔵』山水経を読んだことがある。「而今の山水は、古仏の道現成なり。」私たち学生は「無分別」というキーワードで分析した。一水四見、人間は水と見るものを天人は瓔珞と見、鬼は猛火や膿血と見、龍魚は宮殿や楼台と見る。このようにして人間中心の見方を相対化・分解することで、真実の見方が得られる。その線で読むと、山水経はすっきりと理解できると思った。
しかし先生は、このような分析では不十分で、無分別の先にあるものを考えるようにという。確かに「無分別」というのも言葉による名付けであるので、その先にはきっと言語表現できない世界があるのだろう。あるいはそこから日常に戻ってきて、これまでとは違う視点で新たに世界を捉え直すのかもしれない。いずれにしても、修行もしていない学生には、理解の及ばない話だった。
一水四見の喩えは、「世界は心が作り出したものである」と主張する唯識思想で用いられるもので、禅は唯識から大きな影響を受けている。そもそも唯識思想は「瑜伽師(ゆがし)」と呼ばれる坐禅を重んじる人々によって創立された。唯識の理論を学んでおくことは坐禅の実践に資するところが大きい。
本書は唯識思想の文献を『瑜伽師地論』から『唯識三十頌』まで時代を追って引用・解説することで、思想がどのように展開してきたかを検討する。キーワードは「(虚妄)分別」で、言語表現されない真如の世界の探求から、時代が下るにつれて世界を作り出す心のメカニズムの解明に主眼が移っていく様子と、それが哲学的思惟にとどまらず、衆生を救済するという大乗仏教の精神に貫かれていることを丁寧に描き出している。
唯識思想は三性、三無自性、五事、八識といった難解な項目立てが特徴だが、その源流である『瑜伽師地論』(無著、四~五世紀)の「菩薩地」では、唯識思想の起こりが菩薩行の実践からきていることを示す。菩薩は、対象をすべて差異のないものとして平等に見ることによって、別け隔てなく衆生を救うことができる。見せかけの世界を生み出し続ける分別が消滅することで、見せかけの世界も消滅する「不戯論」の境地になっても、あえて涅槃せずに輪廻を巡って衆生を救い続ける。我が身を振り返るに僧侶が「縁なき衆生は度し難し」というのは、衆生を平等に見る修行が足りていないということだろう。
「菩薩地」は、六波羅蜜をすべて衆生のための修行として捉え、次のように説いている(60~61頁)。一見すると自利行に見える精進・禅定・智慧ですら、衆生を利益するための前準備となっている。
布施:衆生に対して財産と自身の身体を投げ捨てるために、渇愛のない状態をこそ学ぶ。
持戒:他ならぬ衆生のために、律したものとなり、身・語に関して正しく律したものとなる。
忍辱:怒りの少ない者となるために、他者に苦痛を与えない者となるために、忍耐強さをこそ学ぶ。
精進:衆生たちの疑念を除くために、また恩恵を与えるために、また自分が一切智者となるための因を身に付けるために、すべての学処に専心し、習熟した者となる。
禅定:衆生に対してなされるべきことを実行する者となるために、またすべての技術に専心することから生じる苦痛を取り除く者となるために、心の安定を学ぶ。
智慧:最高の真実を知る者となるためにこそ、大乗を学ぶのであり、将来、自分が般涅槃するためではない。
利他行のための無分別は、その後の論書においてもさまざまなかたちで言及される。利他を心がけることによって、修行の境地を深めることもできる。法門無量誓願学、仏道無上誓願成。お釈迦様の教えが修行を支え、またその修行が深まることによってお釈迦様の教えや仏の世界が浄化されるという循環によって全体的に底上げしていく図式が見えてくる。
それにしても無分別とはどのような境地なのか、言語化されない世界とはどのようなものなのなのだろうか。そもそも、あるのかないのかさえもわからない。『解深密経』では、言語表現できない真如の世界を言葉による教説で示す難しさと、衆生を導くため言葉によって伝える努力を説く。道元禅師の「かきもつくべき のりならばこそ」と同じ意識が見て取れる。
ブッダの教えでさえも言葉に過ぎず、概念的なものであるが、そのような言葉の背景には言語表現し得ない本質である事物がある。そして、このことを他人に伝え、その人を了悟に導くためには、言葉に依らざるを得ない。言葉で表現できないものを、あえて言葉で表現するのは、一見矛盾するようだが、その目的は他者の教導にある。/ブッダが悟った真理は、本来は言葉で表現できない深遠な体験に基づいている。しかし、それが言語化されると、あたかもそういうものとして存在するかのように受け取られてしまう。/蘊、界、処や縁起、八正道などの教説はあくまで言葉で説かれた教説であり、ブッダの教えの本質ではない。しかし、言葉としての教説の背景には本質として勝義がある。それは真如であり、法無我と言われる。(133~144頁)
唯識思想は修道論や真如論だけでなく、輪廻のメカニズムも説明している。修行によってアーラヤ識という無意識の影響から自由になり、認識が瞬間瞬間に変化することによって作り出される多様な世界と自己を離れることが、輪廻を断ち切って涅槃に至るということである。
真実の智によって目覚めていない者には、認識の対象が認識表象に過ぎないということがわからない。ブッダでないわれわれは未だ覚醒していない凡夫であり、われわれが現実と思っているものも実は夢のようなものだということになるだろう。(232頁)/われわれは「すでに存在する世界」に産み落とされるわけではないということである。前世の潜在印象を引き継ぎながら、その影響でいずれかの生存状態として生まれ、潜在印象が世界を作り出している。(151頁)/われわれが存在し、認識している世界はすべて、アーラヤ識から現れ出たものと考えられている。さらに、輪廻の中では、アーラヤ識は前世の生存が終わったあと、次の生存において新しい肉体に宿り、あらたな生において認識の機能とその対象を生み出すはたらきをする。(207頁)/善業にしろ、悪業にしろ、前世の業の効力は次の生存状態を決めるところで尽きる。人に生まれるのか、その他の何かに生まれるのか、その新しい生存の状態は前世の業によって決まる。しかし、新しい生存状態に生まれたときには、その前世の業の影響力は失われているので、善でも悪でもない無記の状態になっている。(217頁)
倫理の授業でわからなかった「無分別の先にあるもの」とは、大乗仏教の理念である慈悲心と菩提心ではなかっただろうか。坐禅をして満足するのではなく、坐禅の境地を日常生活にも広げ、悩み苦しむ人に別け隔てなく寄り添う。やがてその人たちにも慈悲心と菩提心が芽生えれば、菩薩の誓願は成就に向かい、仏国土は徐々に浄化されていく。「常に大慈大悲に住して坐禅無量の功徳、一切衆生に回向せよ」(『坐禅用心記』)。