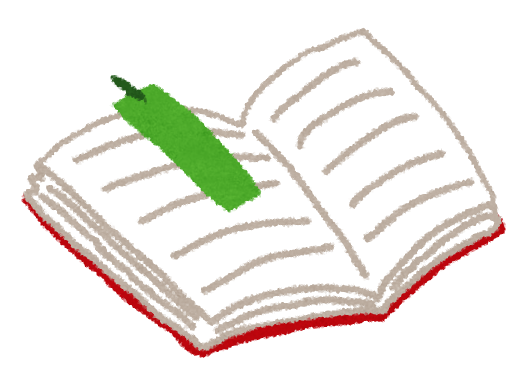著・護山真也/ぷねうま舎(2021年)
大般若会などで理趣分品を読んでいると、いつも励まされるのが次の一句である。お経に書かれた教えを盲信するのではなく、じっくりと「理の如く」考え、その結果納得できるもの、自他ともに役立つものを取り入れなさいという。
若し能く受持して日々に読誦し、精勤無間に理の如く思惟せば彼この生において定んで一切法平等性、金剛等持を得、一切の法において皆自在を得て恒に一切勝妙の喜楽を受けん。
お釈迦様は「私の教えをよく吟味し、深く考えなさい。私への畏敬の念だけで教えを受け入れてはならない」と述べたとされ(出典不明、235頁)、ダライラマは「私の説いた法を君たちは検証し、議論し論理的な根拠に基づいてそれは良いと納得するならば、信仰してもよいものなのだ」と語った(デプン大集会殿におけるダライ・ラマ法王の談話・2019年12月12日)。お経は意味がわからないからありがたいのではなく、曲がりなりにも意味がわかって、納得できたらありがたくなってくるとのだと思う。
仏典を理の如く思惟するための学問として「因明」というものがあるが、日本には法相宗を通じて入ったもものの伝統は失われ、私たちにはほとんど学ぶ機会がない。しかし仏教学では二十世紀になってから散逸していたテキストが見つかるなど、本格的な研究が始まり、現在も多くの学者が国際的に取り組んでいる。本書はその因明を大成したインドの陣那(480~540頃)と法称(7世紀)の「仏教認識論」を、西洋哲学との対比を通して体系的にまとめたものである。人間がものを見、何であるか判断し、記憶し、思い出すという一連の認知過程について、有形象認識論、独自相、仮構、因果効力、自己認識、必然的共知覚といった難解な概念を丁寧に解説している。
なぜこのような問題に取り組むのか、複雑に理論化するのかといえば、仏教徒として、ブッダに迫ろうとする慕古の念があるからだ。そのためには私たちの世界の見方に「癖」があることを知り、迷いを生み出す「分別」を捨てて、認識をゼロから修正していかなくてはならない。そうすることでブッダが悟るまでにたどった道を追体験でき、四聖諦をありのままに見ることができると考える。
私たちの日常的な世界は、あたかも外界対象であるかのように自分たちが習慣的に実体視している対象で構成される。これに対して、瞑想の実践を重ねることは、そのような習慣的に形成されたリアリティを捨てて、ブッダの教説に従うリアリティを新たに重ね描くプロセスである。(20頁)
「一水四見」の喩えが示すように、認識主体が変われば対象も変わる。人間にとっては水であっても、天人にとっては瓔珞となり、鬼にとっては猛火となり、龍にとっては宮殿となる。同じ環境でも見方が異なること、いろいろな環境なのにみんな同じものだと勘違いしているかもしれないことを徹底的に参究するべきであると道元禅師は述べる(『正法眼蔵』山水経)。多様な見方がある中で、お釈迦様のご覧になった真如の世界を、私たちも目の当たりにしたい。その手立ては、瞑想を通してブッダの教説を、あたかも自分が見たもののように現実のものとすることである。
私たちの心は、ともすればそれまでに馴染んだ考えにしたがってしまうのが常である。「諸行無常」の教説にしても、一度聞いてなるほどと思っただけでは、そのことをすぐに忘れ、明日も命は長らえる、という反-無常の考えに引き戻されてしまう。無常性を瞑想するということは、繰り返し何度も「諸行無常」のテーゼを心に念じ、特定のインクの染みが特定の文字にしか見えなくなるように、世界の見方をそうとしてか見えなくなるように固定化することにほかならない。(149頁)
無想禅では「諸行無常」のテーゼを心に念じるようなことを勧めないけれども、坐禅は接心(ブッダの心に接すること)であり、繰り返すことによって「心定に在るが故に能く世間生滅の法相を知る(『仏遺教経』)。」修行によって煩悩の曇りが取り除かれたとき、心は自ずから輝き始めると法称はいう。
このようにして得られたブッダの見方は、心に映じるだけのものではなく、実在の側でその通りに成立しているから真実であるという。しかし神通力をもつヨーガ行者とは異なり、私たちにはそれを確かめることはできない。輪廻転生にしろ悟りにしろ、どこかで必ず、本当かどうかわからないけれども信じてみるという段階がある。盲信してもいけないが、「理の如く」考えることにも限界がある以上、これからの仏教徒にできることは「信仰と理性の中道」であると著者は結ぶ。
仏教認識論は確かに哲学的には興味深いけれども、仏道修行としては心を乱す「戯論」だと思っていた。しかしその背景には、自らを拠り所とし、法を拠り所としてブッダに一歩でも近づこうとする真摯な姿勢があったことを本書は教えてくれる。これからもお釈迦様を礼拝しつつ、「理の如く」お経を読んでいきたい。