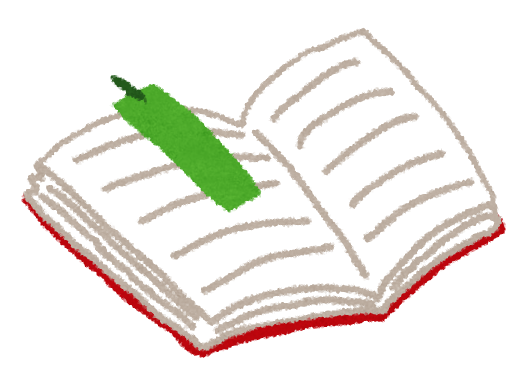著・碧海 寿広/KADOKAWA(2020年)
坐禅や瞑想がうつ病などに効果があると実証されつつある。マサチューセッツ大学医学大学のカバット・ジン名誉教授(1944-)による「マインドフルネス・ストレス低減法」というプログラムが一定の効果があることが分かり、脳科学者たちは瞑想の研究に取り組み、グーグルなどシリコンバレーのIT企業から世界中に波及し始めた。
こういった科学的な説明をされると何かお墨付きをもらったような気持ちになるが、そこには危険性があるかもしれない。本書では「心理学と仏教」「催眠術と仏教」「密教の科学」「禅の科学」「ニューサイエンスと仏教」という章立てで、仏教と科学が結合することのメリットとデメリットを、近現代史から明らかにする。
明治30年、東洋大学の前身を創設した井上円了(1858-1919)が『仏教心理学』を、東京帝国大学教授の元良(もとら)勇次郎(1858-1912)が『禅と心理学との関係』を発表し、西洋心理学から禅の研究が進められた。戦後には脳波測定が取り入れられ、一般や海外向けに坐禅の効能が謳われるようになった。そのうちに「5日間の修行で悟りが体験できる」とか、「LSD(当時は合法だった幻覚剤)が悟りを導く即効薬になる」などという怪しげな話になり、内外から批判を浴びる。ここに宗教体験は科学では把握できないと主張する鈴木大拙(1870-1966)が登場するわけだが、ご興味のある方は本書をお読みいただきたい。
このような坐禅の科学的効能は、仏教にとって現世利益になってきたという指摘は重要である。個人の精神力の増長とか、心や体の病を治すとか、個人の能力や知性を伸ばすとか宣伝されたことで、企業の社員研修や学生の精神修養に取り入れられることになった。坐禅会の参加者にきっかけを伺うと、「集中力を身につけたい」「気持ちが落ち着かない」などといった答えが帰ってくる。そのようなときに坐禅をするといいらしいということがいつの間にか常識になっているのは「科学の成果」というわけである。
坐禅の現世利益を説くのは只管打坐的には邪道かもしれないが、一般の方にとっては方便になっている。しかも単なる方便にとどまらず、坐禅に新しい価値を生み出し、若い世代にも受け入れられるものとなっている(それどころか若い世代にこそ求められているかもしれない)。しかし現世利益を主目的にしてしまわず、その奥にある仏教まできちんと案内することが僧侶の役割であろう。
(『参禅の道』第74号に寄稿)