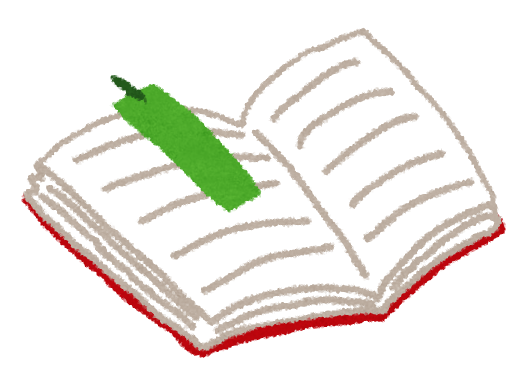『「葬式に坊主は不要」と釈迦は言った』(北川紘洋、1993年)や『葬式仏教正当論』(鈴木隆泰、2013年)などで、僧侶が葬儀を行う根拠と是非が問われてきたが、本書は葬儀を、戒名、慰霊、追善、起塔(墓石の建立)に分け、さらに出家者と在家者に場合分けして、それぞれの起源を初期仏典、大乗経典、密教、中国仏教、日本仏教、南方仏教まで広げて仔細に検討している。仏教以外の文献や、最新の研究成果も踏まえて総合的に考察されており、葬式仏教論の決定版といってもいい内容である。しかも誰が葬式を行うかという話よりも、僧侶への信仰や信頼という観点で論じられており、世俗化した日本仏教で、私達がこれからしていくべきことを考えさせられる。
お釈迦様が亡くなるときの遺言「アーナンダよ、おまえたちは如来の遺体供養にわずらわされるな」「アーナンダよ、如来に対し浄信深い、王族の賢者たちも、婆羅門の賢者たちも、居士の賢者たちもいる。彼らが如来に遺体供養をなすであろう」(大般涅槃経)から、出家者は葬儀に関わるべきではないとも、アーナンダをはじめ未完成の出家者のみ葬儀に関わるべきではないとも理解されてきたが、「おまえたち」と複数になっているのは、あらゆる出家者を指しており、前者(出家者は葬儀に関わるべきではない)が述べられているという。しかし、インドでは出家者の遺体が路傍に捨て置かれたことが世間の非難を浴びるに及んで、軋轢を避けるために葬儀が行われたこともあったらしい。同様に、在家者のまま阿羅漢になった場合に限って、葬儀を行ったケースもある。出家者が一般の在家者の葬儀を行うようになったのは中国・日本でのことであり、インドでは8世紀以降の密教時代までまったく考えられていなかった。つまりインド初期仏教では「葬式に坊主は不要」だったのである。
出家者がお布施を頂いて在家者に引導するという現在の葬儀形態は中国発祥であり、禅宗の僧侶が関わっている。さらに日本では、平安時代から天台宗の僧侶が葬儀を行っていたが、葬儀後に三十日の忌中を守らなければならなかったところに、鎌倉・室町時代になると忌中を守らない禅宗の僧侶によって、皇族、貴族だけでなく庶民に至るまで葬儀が広く行われるようになる。なぜ禅宗の僧侶かといえば、坐禅による「悟り体験」に特別な力があると目されていたからである。
在家者は仏教についてよく知っているわけではない。ただし、禅宗の出家者は悟り体験によってなにか聖者の力を有していると目されていたから、在家者は、聖者の力によって亡者に法語を与えて道理に気づかせ、亡者を転生すべき善趣へ、あるいは証徳すべき涅槃へ、手引きしてもらうことを願って、禅宗の出家者に布施を与えて引導させたらしいのである。(74頁)
亡くなった方に戒名を授けるのは日本で考え出されたことだが、これも聖者崇拝が背景にあるという。『大集経』では「たとえ破戒した僧侶であっても、三宝に対して心が浄信を得ているので、すみやかに涅槃に入ることができるため、あらゆる在家者に勝っている」と説かれ、平安時代から臨終出家や死後出家が求められた。「衆生仏戒を受くれば即ち諸仏の位に入る」と説く梵網経や、ブッダが父である浄飯王の葬儀を行ったと説く『浄飯王般涅槃経』、四十九日の期間内に追善することで善趣に転生すると説く『地蔵菩薩本願経』はいずれも中国で成立した偽経であることが、我々の葬儀や法事の修法がせいぜい中国までしか辿れないことを物語っている。
「悟り体験」が聖者崇拝のもとであり、現代における葬式仏教の衰退は、世俗化により聖者と目される僧侶がいなくなってきたからというのが筆者の見解である。「悟り体験がなく、無心にならずに迷いながらお経を読んだり引導を渡しても、死者の回向にならない」と臨済宗の盤珪禅師はいう。また江戸時代末期に匡道禅師が新命だった頃、ある医師の娘の引導を依頼されたとき、葬儀後に「娘はその一喝で、どこにどう成仏しているのか」と問われ、答えに窮してしまったところ、「この狸坊主!よくも人を騙しおった、自分の安心も出来ずして、しかも我が可愛い娘に引導を授けるとは何事だ」と大盆で打ちのめされた話が紹介されている。匡道禅師はその後修行を重ねて明治時代に臨済宗管長まで務めたが、現代の我々がこのように質問されたとき、果たして自身の修行経験をもとに真摯で納得できる答えを出せるだろうか。
葬式仏教批判は、僧侶が在家者の葬儀に関わること自体を批判しているのではなく、自ら悟りを目指すという本来の仏教の意義を失い、葬儀や法事しか行っていないことを批判しているのだという。逆に言えば、日常的に坐禅を行い、仏典祖録を参究し、利他行に取り組んでいれば、「聖者」とまではいかなくても「この和尚さんにこそ葬儀で引導を渡してもらいたい」と思って頂けるのだろう。そこに将来の希望を見出したい。