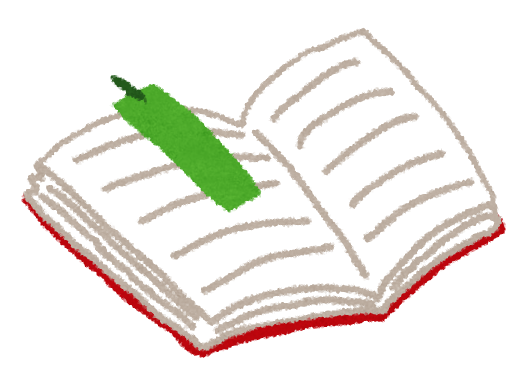道元禅師が最晩年、病気療養のために京都に向かうとき、永平寺の留守を仰せつかった義介禅師に対し、「お前はまだ老婆心が足りないが、歳を重ねれば自然に身につくだろう」と教えられた(『徹通義介禅師喪記』など)。このとき義介禅師は三十五歳。確かに若くて老婆心がないのも無理ないが、道元禅師のこの教えを忘れずに修行に励み、その十四年後、永平寺第三世となられた。
老婆心とは、お節介なほどの世話焼き、必要以上の親切心であり、相手の受け止め方によっては「ありがた迷惑」や「情けが仇」になる可能性もある。若き日の義介禅師は他の修行僧への気配りが足りなかったのかもしれないし、気配りは行き届いていても「これは本当に相手のためになるのだろうか」などと考えて言動をためらうことが多かったのかもしれない。
本書は、仏教を中心にさまざまな視点から利他を見つめる。進化生物学、脳科学、実験社会心理学、倫理学などの現代的な諸相から始まり、ブッダ、大乗仏教、日本仏教を利他という軸で概観した後、さらにキリスト教にも踏み込み、理想の利他として「自我の相対化による自利即利他」を唱える。仏陀が成道の後、梵天勧請を経て説法に踏み切った理由について、著者は次のように述べる。
自分を縁として他者があり、他者を縁として自分があるなら、自分が縁起に目覚めて苦から解脱したことをもって自利が完成したとはならない。真の自利は利他と表裏の関係にある。(中略)ここに他者を利することが自己を利することになるという「自利即利他」の考えが芽生えてくる。(82頁)
日本仏教では行基、空海、叡尊の社会事業が利他行として紹介されているが、単に物質的な援助(「いやし」)だけでなく、精神的に衆生を悟りの世界に渡すもの(「めざめ」)でなければならないという点で捉え直されている。行基は技術者のネットワークを築いて大仏建立を進め、空海は堤工事の残金でお寺を建て、叡尊は網代を撤廃し漁師たちに茶の栽培を勧めた。社会事業自体も方便ではなく、有情と同様に発心・成仏できる無生物(山川草木)への利他行となる。なお、道元禅師について具体的な利他行は現存の資料では確認できないというが、義介禅師に説いた「老婆心」を僧堂の内外で実践していたのではないだろうか。
利他行にあたっては「ありがた迷惑」や「情けが仇」になる可能性をよくよく考えるべきことが、本書でも説かれている。仏教学者の山口益氏は七仏通戒偈の「自浄其意(玄奘訳では「自調伏其心」)」を、「悪を実践しないで、善を実践するという、その私の心をもう一度チェックしなさい、そういう心を浄化しなさい」と解釈し、善の実践の後こそ振り返って、懴悔する必要があると唱えた。臨床心理学者の河合隼雄氏は「他者に善を行わんとする者は、微に入り細にわたって行わなければならない」という。これが「善の懺悔」である。著者は「永遠の微調整」「永遠の過渡期」とも表現している。
誰でも善を実践した後は気持ちのよいものだ。相手に喜ばれて自己肯定感も高まるので、自己満足に陥り、自分を客観的に振り返ることはないが、そこにこそ陥穽が潜んでいる。ここをしっかりと認識して「利他」を実践しなければならない。(35頁)
「坐禅の中に於いて、衆生を忘れず、衆生を捨てず、乃至、昆虫にまでも、常に慈念を給して、誓って済度せんと願い、あらゆる功徳を一切に廻らし向けるなり(宝慶記)」「常に大慈大悲に住して、坐禅無量の功徳を、一切の衆生に回向せよ。憍慢・我慢・法慢を生ずることなかれ。(坐禅用心記)」など、道元禅師や瑩山禅師が説く慈悲は、「自利即利他」という理想的な利他行として捉えるべきだろう。しかし、自他の多様性がどんどん広がっていく現代において具体的な利他を考えるとき、事態はそう単純にはいかない。「己の欲せざる所は人に施す勿れ」といっても、自分がしてほしくないことを相手はしてほしいことや、逆に自分がしてほしいことを相手はしてほしくないことなどいくらでもある。以下は、私が講義をしている短大で、善悪について学生に書いてもらった体験談である。
- 家族の知人の家で「たくさん食べてね」と言われ、食べるのが礼儀だと思って全部食べたら「少しは遠慮しなさい、みっともない」と怒られた。
- コンビニエンスストアで「箸をお付けしますか」と訊くと当たり前だと言われ、訊かないで付けると勝手に付けるなと言われる。
- 飲食店で食べ終わったお皿を下げたり、運転代行サービスを呼ぶか訊いたりしたとき「早く帰ってほしいってことか」と言われた。
- 足を怪我して落とし物を拾うのに苦労している人を手伝ったが、本人ができることに手を出すのは失礼だという考えを後で知った。
黄金律の適切な実践、善の懴悔はますます重要になっている。道元禅師からはまた「老婆心がまだまだ足りない」と言われるかもしれないが、「利行に催さるる」気持ちを常に保ちつつ、相手に寄り添い、相手が何を求めているか、相手のために何ができるかを一々事細かに突き詰めていきたい。