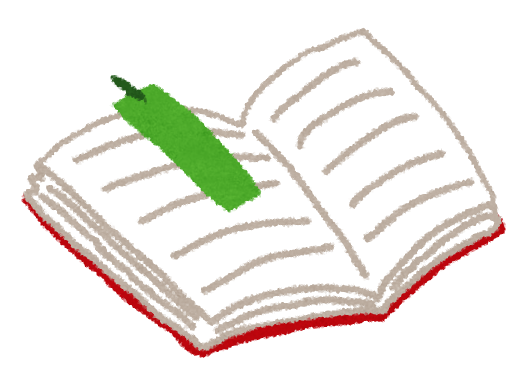平安時代初期、法相宗の徳一上人と天台宗の伝教大師最澄の往復書簡による論争「三一権実諍論」。徳一は三乗説(悟りの道には声聞・独覚・大乗の三つがある)、最澄は一乗説(悟りの道は大乗の一つしかない)を説き、どちらが権=方便で、どちらが実=真実か、その正統性を激しく争った。なぜそこまで争わなければならなかったのかを、当時の日本仏教界の状況だけでなく、中国・インド仏教にまで遡って考察する。
この論争を禅門と関係ない他宗の出来事と捉えてはならない。最澄は、自分の師匠を達磨大師の系譜に位置づけ、禅の教えを学んだと言っており(『内証仏法相承血脈譜』)、道元禅師の血脈とは、五祖の大満弘忍禅師まで共通している(その後六祖において北宗の神秀禅師と南宗の慧能禅師に分かれる)。また道元禅師はかつて天台教学を学び、一乗説を受け継ぎつつも、天台本覚思想に疑問を抱いて入宋し、修証一等=修行が必要な一乗説に至った。「一切衆生悉有仏性」(涅槃経)に由来する一乗説が、どのような議論を経て今日に至るのかを理解することはすなわち、仏教とは何かという、禅宗も巻き込んだ大きな問題に直結する。
さらに禅門では小参や法戦といった問答が現在も行われており、当時の問答の作法や論理は参学に値するだろう。徳一と最澄の論争には共通ルールがあり、両者ともよく知った上で議論していた。その共通ルールとは「因明(仏教論理学)」であり、大学で研究されることはあっても僧侶が学ぶ機会はまずない。本書ではその因明について詳しく解説されている(第四章)。
例えば「共許(ぐうご)」というルールは、議論の前提を、対論者の両方が共に承認していること、あるいは当時の仏教界で一般常識となっていることである。独りよがりな解釈や、相手が理解できない言葉で煙に巻くのはルール違反となる。「自教相違」は、自分が拠り所とする学説と矛盾する主張をすること、「自語相違」は自分の主張の中の自己矛盾、「立已成(りゅういじょう)」はすでに常識的なことを改めて主張することで、こういった過失を犯すと相手から批判されることになる。このようなルールの目的は相手を言い負かすことではなく、「相手の頭のなかに、相手が知らなかったことについての”智”を生じさせ、納得させよう」ということであり、人々を悟りへと導く大乗の精神、利他行であるともいう。スポーツのルールも、反則を罰することが目的ではない。
究極の心理に至る道程には、言葉で解決すべき無数の問題が横たわっている。仏道を歩む者は、最後には言葉を捨てるとしても、それまでは言葉を使って性格に教理を理解し、言葉を使って高僧と問答をし、言葉を使って誰かを説得しなければならない。(百六十頁)
禅門の法戦式などで、問答がこのような因明のルールに則っているかといえば、一般常識の無視、不可解な用語の使用、伝統学説との矛盾、自己矛盾、当然なことの主張で溢れており、わざと反則を犯すことで究極の真理に到達しようとしているのではないかと思うくらいだ。もしかしたら因明のルールに則ってじっくり理解していくのは北宗禅の「漸悟(段階的に悟りを進める)」、ルール無視で直接理解しようとするのは南州禅の「頓悟(一気に悟る)」の違いが背景にあるのかもしれない。それはそれでひとつの伝統なのかもしれないが、一足飛びに真理を目指すのではなく、初歩的なところから理解を固めていく必要もあるのではないだろうか。
曹洞宗では近年、宗侶・寺族が新宗教などの教えに傾倒し、場合によっては入信にまで至っている事態が起こっていることを問題視し、現職研修会などでの啓発に取り組んでいる。その要因として、信仰心の未決着、流行への飛びつき、自宗の不勉強、寺院維持の困難などが挙げられており、決して個人の問題ではないことがわかる。由々しき事態ではあるけれども、相承されてきた仏法を内外に伝えていくためには、攻撃的にならず、ルールに則って理性的に議論していくことが望ましい。紀元前に仏教を守護したアショーカ王は次のように述べている。
「不適切な状況で、自分の属する宗派を称揚し、他の宗派を貶めるような言葉は控え、適切な状況でも穏当であること。いかなるときでも、他の宗派には正当な敬意を支払うべき。非難は特別の理由があるときのみ許される。なぜなら他の宗派は、理由は異なっても、どれも尊重に値するからである。自らの宗派に敬愛を捧げる一方で、他の宗派については、自らの宗派への愛着を理由に貶める者は、このような行為によって、実際のところ、己の宗派に最も甚大な損害を与えているのである」(アショーカ王碑文)