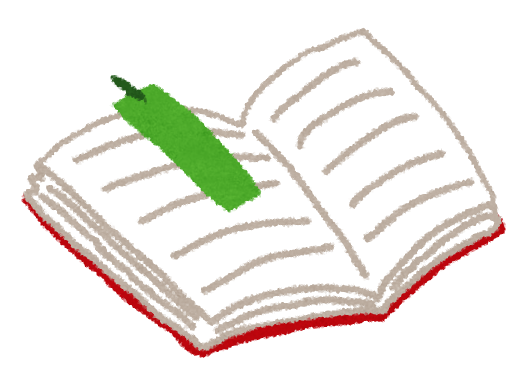著:中村岳志/ミシマ社(2021年)
利他というのはどうも胡散臭く捉えられるきらいがある。お坊さんがすました顔で「誰かのためを思って送る生活こそ真の幸せ」と説いても、じゃああなたは誰のためを思って毎日過ごしているんですか、結局のところ自分が裕福であればよいと思って利益誘導してませんかという冷たい視線は避けがたいもの。本書もそんな胡散臭さを前提として利他について考察をめぐらす。
落語「文七元結」は、借りた五十両を通りかかった若者にやってしまったという人情噺。どうしてそんな大金をぽんとやってしまったのか。立川談志は安易な「共感」という解釈を拒絶しつつも、最後まで決着がつけられなかったという。筆者はここに「業の豊かな不可解さ」=大きな世界観の中で、無意識のうちに、不可抗力的に機能するもの、「利他」と認識されない「利他」を見る。これがタイトルにもなっている「思いがけず」である。「彼が報謝を求めず、唯単えに利行に催さるるなり」(道元)という言葉が受け身で書かれているのを思い起こす。
北アメリカ先住民であるチヌーク族では、祝宴に招いた人たちにお返しができないほどの贈り物を渡す「ポトラッチ」という風習。相手に負債感を与え、服従させるという意図があり、贈り物は支配/被支配の論理をもつという。贈り物や親切をする時、自分に見返りを求めるつもりはなくても、相手には負債感を与えてしまう可能性は十分に考えておかなければならない。持ちつ持たれつ、時には遠慮せず親切をしてもらうことも必要である(そういう意味では、お寺が頂いても負債感を持たないごっつぁん体質だというのはいいのかも)。
利他は与えた時に発生するのではなく、受け取られた時にこそ発生するものであり、与え手は利他的であるか否かを決定できない。何かをきっかけに「あのときの一言」「あのときの行為」の利他性に気づいたときはじめて、利他が起動すると筆者は指摘する。亡くなった人には生前、数え切れないほどの言葉や行為があったわけだが、それを誰かが何年、何十年か後に気づくことではじめて利他になるわけだ。中には気づかれないまま忘れ去られていくこともあるだろうが、命日やお盆や年回忌に思い出して1つでも多く回収するのが遺された者の務めではないだろうか。
『歎異抄』の「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」という言葉から、現代日本の行き過ぎた自己責任論に最も欠如しているものは、自分が「その人であった可能性」に対する想像力だと筆者はいう。自分が今このようにしているのはたまたまなのであって、犯罪者になっていたかもしれないし、とっくに死んでいたかもしれない。これからも生き続けるかすぐ死んでしまうか、どんな人生になるかわかりませんが、それは他者次第であることを銘記し、自己を過信せず、他の人とよい関わりをもっていきたいと思う。
なおヒンディー語の与格から「オートマティックな構造」(縁起思想)を説くのは論証不十分な感じ。