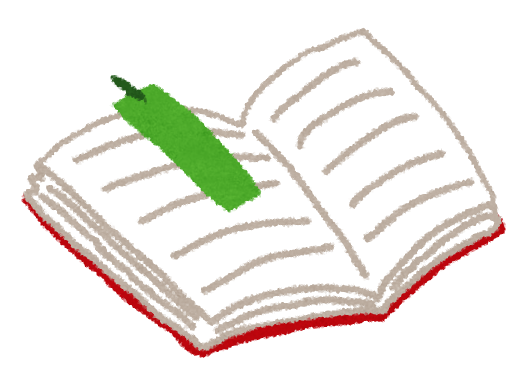小林武彦著・講談社現代新書
生物学者が生命の発生と進化の歴史を説明しつつ、生物の死とヒトの死を対比し、その理由を考察する。
タイトルの答えは多様性。さまざまな環境を生き抜いてきた種は、古いタイプを壊してその材料や環境を再利用して多様な「試作品」を作ってきた。仮に一個体が長生きすればするほど、新しい試作品を作る機会が減り、環境の変化に対応できない。環境が変わったときの不具合を、個体ごと交換するという方法(「ターンオーバー」)でアップデートしてきたからこそ我々の今があり、今後も、地球温暖化などの環境変化に対応する個体をどれくらい増やしていけるかが、生き残りのカギになるだろう。「後生畏るべし」である。
当然ですが、子供のほうが親よりも多様性に満ちており、生物界においてはより価値がある、つまり生き残る可能性が高い「優秀な」存在なのです。言い換えれば、親は死んで子供が生き残ったほうが、種を維持する戦略として正しく、生物はそのような多様性重視のコンセプトで生き抜いてきたのです。(174頁)
省エネ体質と護衛・食料調達・子育て・布団係などの分業で30年も生きるハダカデバネズミにならって長寿を目指したとしても、ヒトには死の悲しみや恐怖がある。しかしそれは共感力の賜物であり、集団を大切にし、他者とのつながりによって生き残ってきた以上、逃れる方法はない。人とつながる幸福感と死の悲しみは表裏一体、幸福感だけを取ることはできない(だからお釈迦様は、どちらも捨てて独りでいることを勧めている)。しかし自分の死が、次世代(血がつながっていなくてもよい)の礎となるならば、死の悲しみは和らぐのではないか。事実、多くの人の死を礎にして今の自分があるのだから。
其の未だ度せざる者には、皆亦已に得度の因縁を作す。自今已後、我が諸の弟子、展転して之を行ぜば、即ち是れ如来の法身常に在して而も滅せざるなり。(仏遺教経)