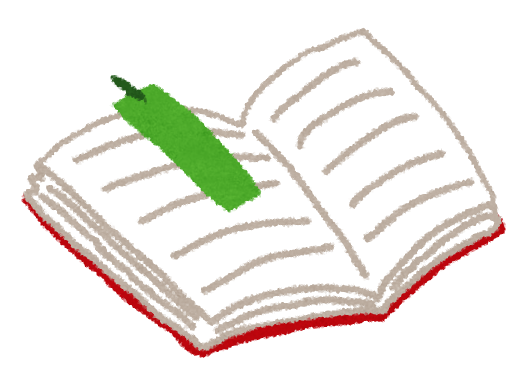伊藤亜紗編、集英社新書。晋山結制式のテーマである因果について考えていたとき、たまたま目について読んだ。人の幸せを思い、喜んでもらうことは、人生の目的とするのにふさわしいものではあるが、「小さな親切大きなお世話」「ありがた迷惑」というように、自分は良かれと思っても相手に喜んでもらえないことが多々あって一筋縄ではいかない。本書は東京工業大学・未来の人類研究センターの研究会「利他プロジェクト」に携わる五人が、さまざまな専門分野でこの問題を論じたものである。
「人の幸せ」は抽象的なものではなく、特定の誰かの幸せである。何が幸せで、何が喜びなのかは、人によって大きく異なるため、まずはその人の理解が必要になる。しかし理解以前に、信頼が大切である。悩みや苦しみを乗り越えていくのは本人。相談にのるとき、その人の力を信じるという話を思い出す。
目が見えなかったり、認知症があったりと、自分と違う世界を生きている人に対して、その力を信じ、任せること。やさしさからつい先回りしてしまうのは、その人を信じていないことの裏返しだともいえます。(48頁)
相手を信頼した上で、理解のために傾聴する。相手のものの見方が自分と違って当然という前提は忘れやすい。しかし自分の常識にとらわれていては、相手の理解は覚束ないだろう。「計画倒れをどこか喜ぶ」態度が重要だという。そう思えるには、自分の中に心の余裕がなくてはならない。
どうしても私たちは「予測できる」という前提で相手と関わってしまいがちです。「思い」が「支配」になりやすいのです。利他的な行動をとるときには、とくにそのことに気をつける必要があります。(54頁)
返礼をしなくてもよいことは一見すばらしいことだが、人類学者M.サーリンズはこれを「権力の萌芽」であるという。返礼をしなくてよいことから優越感や負債感が生まれ、社会の階層化につながるからである。中島岳志氏はインドで「ありがとう」と言ったらキレられた経験から、純粋な贈与(優越感も負債感も生まない利他)の可能性を考察している。見返りを求めず、思わずやってしまうこと。そこでは自我への囚われは邪魔になってしまう。「彼が報謝を求めず、唯単えに利行に催おさるるなり(道元禅師)」である。
自分の個を超えた力に促されて生きていることを、仏教の世界では「業」と考えてきました。業とは、後ろから押す力、何かオートマティックな力です。そして、このような自分の意思とは違う何かが働くという問題を考えないと、利他の核心に迫れないのではないかと私は考えています。(96頁)
しかし仏教で業(本能的なもの)は善悪を問わずいったんリセットするべきものである以上、自我への囚われを捨てても、業に支配されていては「利己的な利他」の落とし穴から抜け出せない。中島氏は阿弥陀仏による「他力の利他」をもちこむが、仏の教えに基づく主体的な生き方の中でなされる「自力の利他」の可能性も十分考えられるのではないだろうか。