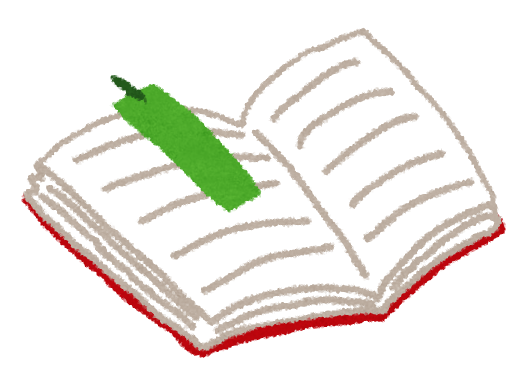久しぶりにマッツァリーノが読みたくなって調べたら、出版からもう3年も経っていたが、中身は全然古くないどころか、「選択的夫婦別姓反対論は理由なき反抗」は今こそ読むべきものだった。
非常に多くの反対派が理由としてあげていながら、夫婦別姓にしたことで絆が壊れた家族の実例を示しているひとがひとりもいないのです。似たような理由で、「別姓にするとこどもがかわいそう」という意見も多いのですが、その「かわいそうなこども」の実例も、まったくありません。それって、どう考えてもおかしいですよね。日本以外の世界中の国では、別姓にしてる夫婦がごまんといるのだから、もし、別姓が原因で家族の絆が壊れるのなら、実例なんていくらでもあげられるはず。かわいそうなこどもだって大勢いるはずです。(中略)もし、夫婦別姓に致命的なデメリットがあるのなら、海外でもとっくのむかしに存廃議論が起きてるはずです。こどもの人権侵害を監視する団体が、不幸なこどもを守れと必ず声を上げているはずです(p.268)。
本書のテーマはクリティカルシンキング=「自分が常識と思ってること、正しいと信じてることが、誤った前提や偏見で歪められていないかどうか、つねに疑いながら、正しい客観的根拠と正しい論理によって、対処法や解決法を考える現実的な思考法」(p.365)「デマやイデオロギーにとらわれず、客観的な事実をもとにものごとを考えられるひと。意見や立場の異なる相手ときちんと議論ができるひと。理性や知性のみならず、自分も保守も(その他の政治的思考も)万能ではないと認め、自分がまちがっていたとわかれば主張を改めるのも厭わないひと。」(p.353)で、無批判に受け入れている前提や偏見を「思考の憑きもの」と呼んでいる。
本書で出てくるのは「出羽守もときに必要」「匿名だから悪いわけではない」「自由には責任が伴わない」「万が一ではなく適切なリスク評価に基づいた行動を」「反日という人の正体は自家中毒」「リベラル保守もいる」など。以前の著書の「昔は良かった病」「凶悪犯罪は増えていない」などに加えて、疑問を呈したい「常識」がまた増えた。
事実はひとつ(検証によってひとつに絞ることが可能)だが、事実に解釈を加えた物語が「真実」なので、真実は複数存在する(p.193)、自分が信じたいものだけを信じるようになったひとは、不思議なことに、自分が信じるだけでは満足できず、自分の価値観を他人も信じるよう、強制し始める(p.357)というくだりは、仕事でも気をつけたいところ。
マッツァリーノを愛読してきたせいか、常識(とされていること)を疑う癖はついているように思うが、意見や立場の異なる相手ときちんと議論ができるかというと自信がない。話の腰を折って恨まれるくらいなら議論を回避して、せいぜい他山の石にするくらいくらいだが、こういう思考法を建設的な方向に役立てたいものである。