 口伝というのは、譜面には直接的に表されていない慣用的な約束事です。どういう約束かは、口伝ゆえに書かれておらず、また諸説あるようですが、それでも全く自由にというわけではありませんので一般的なところを考察します。
口伝というのは、譜面には直接的に表されていない慣用的な約束事です。どういう約束かは、口伝ゆえに書かれておらず、また諸説あるようですが、それでも全く自由にというわけではありませんので一般的なところを考察します。
紫雲
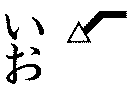
「草の庵に」の「いお」です。私は子供のときからこれを聞いて「草の世に」だと思っていました。「い」をできるだけ長めにとらないと「よ」に聞こえます。しかし直後には基本のアヤも控えており、あまり伸ばしすぎると3・1になってしまいます。そこで2・2の最初の2を1・1に分割し、「い」・「お」と割り振るわけですが、気持ちとしては「い」を長め、「お」は発音したらできるだけ早くアヤとするとちょうどいいようです。
ちなみに2・2の最初の2を1.5・0.5に割り振って「お」の始まりを音尾アヤにするという方法があるらしいですが、少し変な気がします。
観音菩薩御和讃
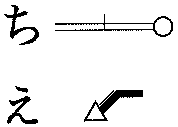
「まどかに智恵は」の「ちえ」です。こちらの口伝は発音が変わるにも関わらず、音尾にアヤを入れるという難解なものです。もうひとつ「観世音」の「かん」で音節の変わるところで音尾のアヤが入ります。
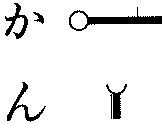
この例は次の音が母音または「ん」であるため比較的楽にアヤを入れることができます。母音の場合口の形を変えるだけで、また「ん」の場合は喉を飲み込む形にするだけで発音を変えることができるからです。
しかし問題は2番「迷いはまこと」の「まこ」、4番「うれしさあまる」の「あま」です。子音が入るため音の変わり目が明確で、音尾アヤの直後に瞬間的に発音を変えるのは至難の技です。いくら努力してもタイムラグが出てしまいます。最大の難所といってもいいかもしれません。
注記:当初この口伝は基本のアヤとして音頭も入れると思っておりましたが、谷口充洋師のご指摘により音尾のみであると判明しました。指導必携にも「言葉が変わるが音尾のアヤを入れる」「(前音を指して)アヤを入れる」と書かれており、音頭のアヤはないと解釈されます。お詫びして訂正すると共に、ご指摘頂きました谷口師に感謝申し上げます。(2002/4/10)